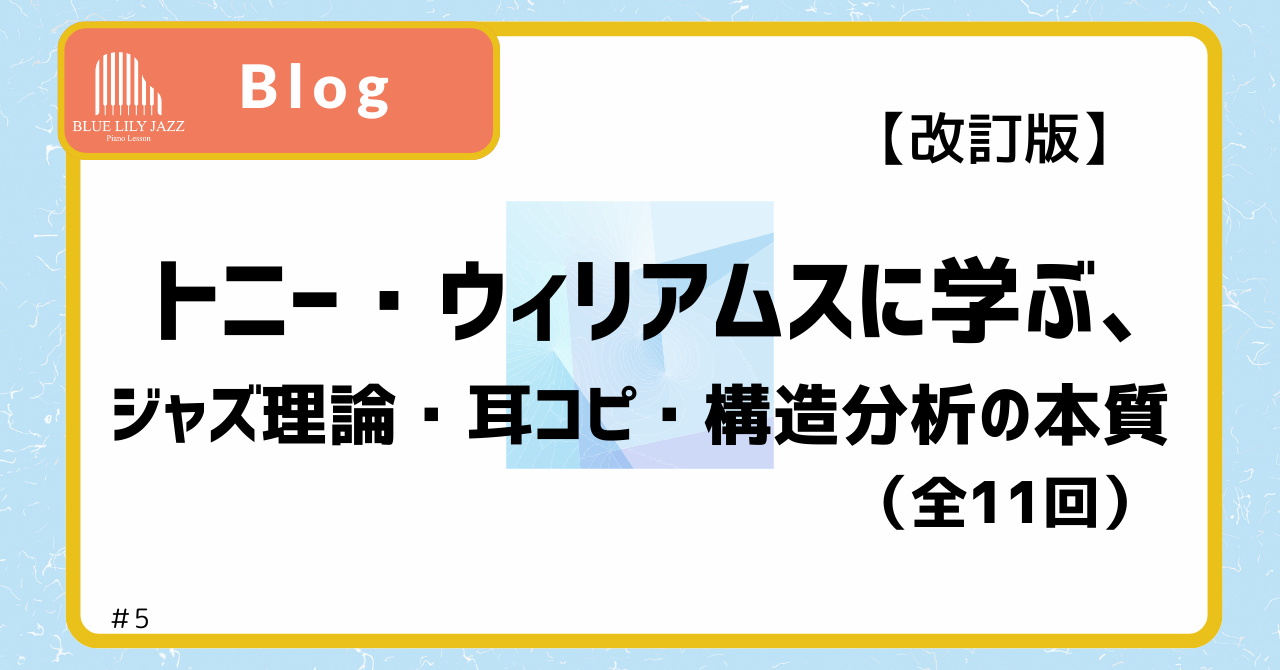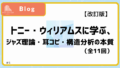第2回:なぜトニー・ウィリアムスは作曲家になろうとしたのか?
トニー・ウィリアムス、マイルスのバンドで感じた孤独と“書くこと”への衝動
天才少年の「空っぽな夜」
インタビュアー:1963年、17歳でマイルス・デイヴィス・クインテットに入ったトニー。
まさに伝説の始まりですよね。最年少でジャズの頂点に立った気分はどうでしたか?
トニー:いや……むしろ、めちゃくちゃ不安だったよ。
もちろん光栄だった。でも、自分がそこにいる理由がわからなかった。
演奏している間は、ちゃんと存在できてる感じがあった。
だけど、ステージを降りたら、自分が“そこにいていい人間”なのか分からなくなるんだ。
楽屋、移動中のバス、ホテルの廊下――全部がよそよそしかった。
インタビュアー:17歳って、まだ高校生の年齢ですもんね。
トニー:そう。マイルスも、ハービー(ハービー・ハンコックをAmazonで聴く)もロン(ロン・カーターをAmazonで聴く)もみんな大人だったし、音楽理論にも詳しかった。
それに比べて、自分はただの“叩ける子ども”だった。
「俺がドラマーじゃなかったら、この人たち、俺に話しかけたかな?」って思ってた。
その思いは、ずっと消えなかった。
☆トニーから学べること☆
どれだけ才能があっても、「ここにいていいのか?」という不安は消えないんですね。
彼にとってドラムは“場にいる理由”だったけれど、同時にそれしかないことが怖かったんだと思います。
表現者である前に、人として“自分をどう在らせるか”という問いがあったんだと思います。
トニーが参加しているマイルス・デイヴィス・クインテットのアルバム
・Miles Smiles(Amazonで聴いてみる)
※『Miles Smiles』は、トニー・ウィリアムスが作曲に目覚めた時期の代表作。彼の構造的アプローチがドラムだけでなく楽曲全体に現れています。
・Miles In Berlin(Amazonで聴いてみる)
演奏だけでは語れない“もうひとつの自分”
インタビュアー:その「不安」や「空虚感」は、どうやって解消していったんですか?
トニー:最初はどうしようもなかった。でも次第に、自分の中にもう一つの欲求が生まれたんだ。
“自分の音楽をつくりたい”っていう気持ち。
ドラムって、その場で即興して、反応して、空気を読むものだろ?
それはそれで魅力的なんだけど、俺はもっと時間をかけて考えたいと思ったんだ。
「何かを生み出すこと」で、初めて“トニー・ウィリアムス”っていう人間になれる気がして。
インタビュアー:それが“作曲”につながっていった。
トニー:そう。書くことは、俺にとって自分自身を再構築する方法だった。
☆トニーから学べること☆
多分、演奏だけでは語れないことって、誰の中にもあるんだと思います。
トニーは、即興では掬い取れない感情や哲学を「構築する」ことで表現したかった。
それが、作曲というもう一つの“言語”を選んだ理由だったんでしょうね。
☆作曲に関する理論書☆
▶ トニーのように“構造”から音楽を構築するために:
・『ジャズにおける作曲の理論と実践 ジャズ・コンポジション』(Amazonで詳しく見る)
2本の指で学んだトニー・ウィリアムス流ジャズ作曲法
インタビュアー:作曲って、最初からできたんですか?
トニー:いや、まったく(笑)。ピアノも弾けなかった。
最初は右手と左手、それぞれ1本の指しか使えなかったよ。
インタビュアー:それで、どうやって曲に?
トニー:ただ、メロディの動きやフレーズの輪郭は耳で分かってた。
それを2本の指で探しては、録音して、ハービーに渡したりしてた。
彼がコードを補ったり、僕の意図を読み取ってくれたりして、曲が少しずつ形になった。
インタビュアー:具体的には、どんな工夫を?
トニー:たとえば、4小節のフレーズがあったとして、それを反復するだけじゃ弱い。
途中で転調させたり、リズムを変えたりして、構造を変化させるんだ。
ABAの三部形式にしたり、終止にサブドミナントマイナーを入れて柔らかくしたり。
そうやって、“展開”という思考を覚えていった。
☆トニーから学べること☆
きっと彼は、演奏とは違う“時間の流れ”で音楽を見たかったんでしょうね。
即興が「今ここ」の対話だとしたら、作曲は「全体を俯瞰する地図」。
限られた技術の中でも、彼は“構築”することの面白さに気づいていたのだと思います。
音符を並べることで、心が整理される
インタビュアー:作曲って、精神的にも何か変化を与えてくれましたか?
トニー:うん。作曲は、ある意味で“内省の行為”だった。
ニューヨークにいた頃、セラピーにも通ってたんだけど、それと同じような感覚があった。
テーマを書いて、展開部を考えて、エンディングにたどり着く。
そのプロセスが、自分の思考を整理してくれるんだ。
「今、自分は何を感じているのか」が、音の選び方に出る。
インタビュアー:無意識の感情が、メロディやコードに現れる?
トニー:そう。とくに“間違った”音を選んだとき、自分の混乱を感じる。
逆に、しっくり来る進行が見つかると、「ああ、これが今の自分なんだ」って分かる。
☆トニーから学べること☆
音楽は、ただのアウトプットじゃなくて、“思考と感情の整理”でもあるんですね。
作曲することは、譜面を書く行為であると同時に、自分の内側と向き合う時間でもある。
きっと彼にとってそれは、演奏とはまったく別の“自分と話すための手段”だったのでしょう。
理論は、“感じたもの”を伝えるためにある
インタビュアー:作曲を学ぶ過程では、理論も本格的に学ばれたとか。
トニー:そうだね。スケール、ハーモニー、対位法、モーダルな考え方……全部やった。
でもね、理論って“感じたものを他人に伝えるための言葉”だと思ってる。
インタビュアー:最初に感じたことがあって、それに理論が追いついてくる?
トニー:そう。
作曲をしていると、「この感じ、名前は分からないけどすごく必要だ」っていう瞬間がある。
あとから「それはディミニッシュ・スケール上の代理コードだったんだ」と気づく。
それがうれしいんだよ。感覚と理論がつながったとき、“わかった”って実感できる。
☆トニーから学べること☆
理論は、ただのルールではなく“気づきを整理するツール”なんですね。
彼のように、まず感覚を信じて動き、そのあとで言語化することで、理解が深くなっていく。
理論は“冷たいもの”ではなく、“感覚に寄り添ってくれる知性”なんだと思います。
☆オススメ理論書☆
・『マークレヴィン ザ・ジャズ・セオリー』(Amazonで見る)
次回予告:第3回 2本の指が描いた“構築の美学”
ハービー・ハンコックとともに生まれたトニーの初期作品群
第3回では、トニー・ウィリアムスの初リーダー作『Life Time』に迫ります。
ピアノが弾けない状態でも、構造を重視して生み出された楽曲たちは、
ハービー・ハンコックらとの共演によって、どのように音になっていったのか?
「未完成だからこその強さ」が宿る創作の現場を描きます。
☆トニー・ウィリアムスの初リーダー作『Life Time』をAmazonで聴く
次回もお楽しみに!
ブルーノート・ベスト・ジャズコレクション高音質版 44号 (トニー・ウィリアムス) [分冊百科] (CD付) (ブルーノート・ベスト・ジャズコレクション 高音質版) (Amazon)
【このシリーズの他の記事】
文・構成:浦島正裕(ジャズピアニスト/音楽理論講師)
ピアノと言葉を通して、日々、音楽の仕組みと心の動きの接点を探し続けています。
音楽の音にある「理由」を、常に多角的に考えています。
☆『THE PALM OF A BEAR』/浦島正裕
【クリエイティブノート】この連載は1992年にMusician Magazineに掲載されたTony Schermanによるインタビューを参考にし、独自の再構成と解釈を加えたフィクション形式の記事です。実在の発言内容を基にしていますが、構成上の演出や編集が含まれます。ジャズを学ぶ読者の学習と創造力を促す目的で制作しています。