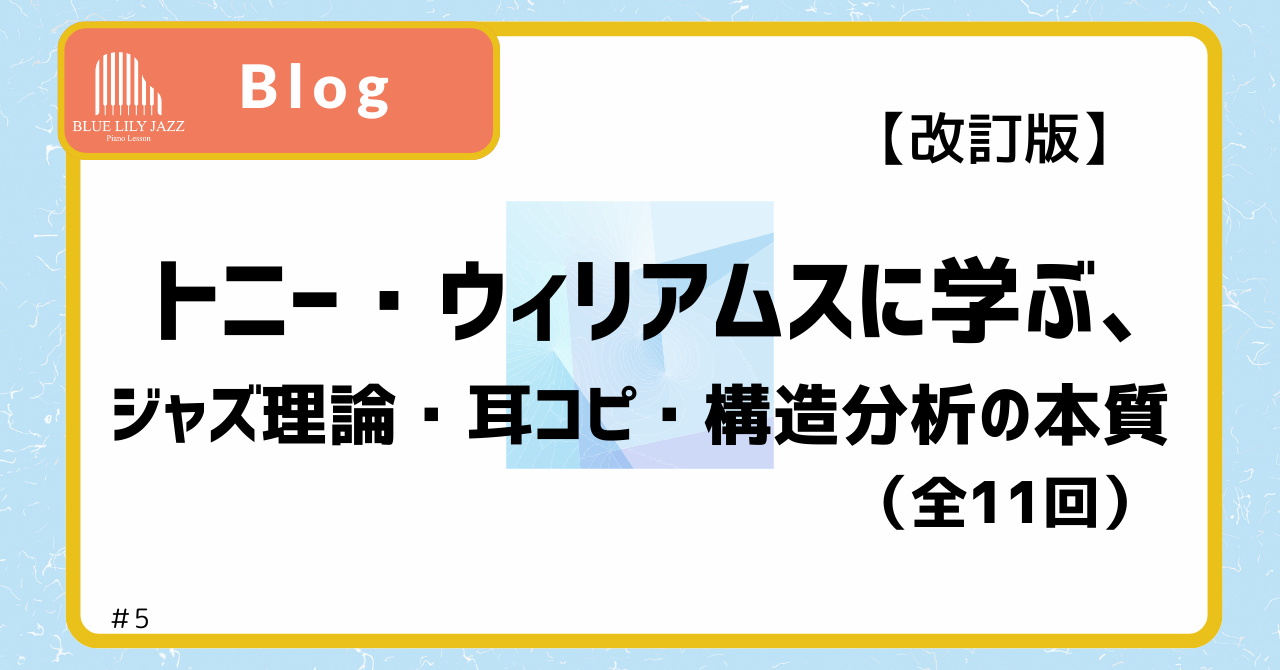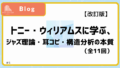スタイルに走る前に、誰かになりきってみろ!
「自分らしいサウンドが欲しい」
「人と違う演奏がしたい」
これは多くのジャズ学習者が最初に抱く願いかもしれません。現代では特に、“オリジナリティ”が良いことだとされ、真似することはどこか後ろめたいような印象すらあります。
でも、もし“自分らしさ”の土台が何もなかったとしたら?
その演奏は、誰にも届かないただの独りよがりになってしまうかもしれません。
トニー・ウィリアムスは、そんな問いに真正面から向き合った人物です。
17歳でマイルス・デイヴィス・クインテットに抜擢されたジャズ界最年少の革命児は、自分のスタイルを手に入れるまでに、徹底的な「模倣の旅」を経験していました。
トニーが参加しているマイルス・デイヴィス・クインテットのアルバム
・Miles Smiles(Amazonで聴いてみる)
・Miles In Berlin(Amazonで聴いてみる)
インタビューを基にその足跡を辿ります。今回は、その出発点に迫ります。
第1回:マックス・ローチになりきるということ
トニー・ウィリアムスに学ぶ、“真似る”ことでしか得られない音楽の根っこ
スタイルの前に「誰か」になること
インタビュアー:トニー、ドラムを始めたばかりの頃って、どんな風に練習していたんですか?
トニー:13歳だったかな。最初の2年間は、マックス・ローチ(Amazonで聴いてみる)になりきってたよ。
もう本当に、“彼のコピー”じゃなくて、“彼そのものになる”ってつもりで、レコードと一緒に叩いてた。
インタビュアー:マックス・ローチ(Amazonで聴いてみる)のどこがそんなに響いたんですか?
トニー:音楽としての完成度。ドラムがリズムじゃなくて、構造を持った“演奏”になってる。
ソロもコンピングも、まるでスピーチみたいに起承転結がある。
たとえば、1コーラスのソロでも、ABA構成のようにフレーズを対比させてたりする。まるで作曲のようだった。
☆トニーから学べること☆
きっとトニーは、ドラムを“話す楽器”として捉えていたんですね。
ただ叩くだけでなく、構成や対比、テンションの配置まで考えていた。
つまり彼の模倣は、すでに「音楽理論的に分析しながら再現すること」だったのかもしれません。
耳コピと構造理解で模倣を深める
インタビュアー:他にもコピーしていたドラマーはいますか?
トニー:アート・ブレイキー、フィリー・ジョー・ジョーンズ、ジミー・コブ、ロイ・ヘインズ……
みんな“何を言っているか”が違った。
ブレイキーはとにかく強くて、スピリチュアルな推進力がある。(ブレイキーをAmazonで聴く)
フィリー・ジョーはリズムでメロディを描く天才。(フィリー・ジョーをAmazonで聴く)
ジミー・コブのタイム感には、空間を読む深さがあった。(ジミー・コブをAmazonで聴く※Joe Hendersonのアルバム。ジミー・コブがとても良いです!)
ロイ・ヘインズは“跳ねる知性”。自由に浮遊してるけど、ぜんぶ論理的なんだ。(ロイ・ヘインズをAmazonで聴く)
インタビュアー:それぞれの演奏を全部耳で真似した?
トニー:うん。でも“音”を真似るだけじゃ足りなかった。
「なぜこのフィルがここにあるのか」「このタイム感は何を支えているのか」――そこまで感じ取らなきゃ、意味がない。
テンションの流れとか、リズムの中での役割とか、コード進行との兼ね合いも耳で追ってた。
言ってみれば、“耳で理論をなぞっていた”ってことかもね。
☆トニーから学べること☆
多分、模倣というと「ただ真似するだけ」と思われがちですが、
彼の場合は「なぜそうなるか」を考えながら真似していたんでしょうね。
それってまさに、構造分析=理論的思考です。耳を通して理論を感じる、というアプローチだったんだと思います。
コピーが教えてくれる、自分の弱点
インタビュアー:模倣のなかで、自分の課題にも気づいたりしましたか?
トニー:めちゃくちゃあったよ。
マックスのような構築感が出せない。ブレイキーみたいな説得力もない。
フィリー・ジョーみたいに、コードの動きに合わせてラインを乗せるセンスもまだなかった。
でも、だからこそ「もっと知りたい」「構成を理解したい」って思えた。
インタビュアー:つまり、模倣は“次の学び”の道を教えてくれる。
トニー:そう。真似をしていると、知らないことがはっきりするんだよ。
「ここでモーダルな考え方が必要だな」とか、「あ、ここはポリリズムっぽい構造になってるな」って気づける。
それが、理論を学ぶ“動機”になった。
☆トニーから学べること☆
きっと彼は、真似することで「自分に足りない知識」を自然に自覚していったんですね。
そしてその空白を埋めるように、理論を後から学んでいった。
模倣 → 違和感 → 理論の習得、という流れは、とても健全な学び方だと思います。
☆オススメ理論書☆
・『ジャズにおける作曲の理論と実践 ジャズ・コンポジション』(Amazonで見る)
・『マークレヴィン ザ・ジャズ・セオリー』(Amazonで見る)
理論は“音楽を言語化するため”にある
インタビュアー:理論は後から学んだとのことですが、どうやって習得していったんですか?
トニー:ちゃんと先生について勉強したよ。スケール、和声、対位法、コード進行、全部。
たとえば、自分がよく耳で感じてた“動き”に、実は名前があることがわかっていった。
「この感じはサブドミナント・マイナーだったのか」とか、「ここは転調というよりモーダルシフトだったのか」とか。
インタビュアー:つまり、理論は“翻訳”だった?
トニー:そう。音で感じていたことに、言葉を与える作業。
逆に言えば、理論を学ぶことで、自分の感じ方を“他人に伝えられるようになる”。
特にバンドでやるときは、コミュニケーションの武器になるよ。
☆トニーから学べること☆
理論を“後から”学ぶのではなく、“後からでも”学ぶことが重要なんですね。
感じたものに名前を与えることで、自分の表現を他人と共有できるようになる――
それが理論の持つ、本質的な意味なのだと教えてくれている気がします。
☆オススメ理論書☆
・『ジャズにおける作曲の理論と実践 ジャズ・コンポジション』(Amazonで見る)
・『マークレヴィン ザ・ジャズ・セオリー』(Amazonで見る)
模倣は、個性をつくるための土台になる
インタビュアー:真似をし続けると、個性がなくなるんじゃないかって不安に思う人もいます。
トニー:でもそれは逆だよ。どんな演奏者をどういう風に模倣したか――
その“履歴”がそのまま君の音になる。
僕の演奏が“トニー・ウィリアムスらしい”って言われるなら、それはマックスやブレイキーを丸ごとコピーした時間があったから。
☆トニーから学べること☆
真似ることは、個性を失うことではなく、個性の“素地”をつくる行為なんですね。
「誰を真似たか」「どこまで真似たか」が、のちの表現にそのまま現れる。
模倣はスタイルの材料であり、理論はそれを組み上げる設計図なのかもしれません。
【模倣】の重要性について書いてある書籍
新版 学校を改革する──学びの共同体の構想と実践/佐藤学(著)
※JAZZではありませんが、佐藤学氏は「模倣」という言葉を明確に使用し、その重要性を教育実践の中で強調しています。
次回予告:なぜトニー・ウィリアムスは作曲家になろうとしたのか?
17歳のトニーがマイルス・バンドで抱えた孤独と葛藤
第2回では、マイルス・デイヴィス・クインテットに加入したばかりのトニー・ウィリアムスが、
“天才”と呼ばれながらも感じていた自己否定、バンド内での疎外感、
そして“作曲”という新たな言語を見出していく過程を描きます。
次回に続きます。お楽しみに!
【このシリーズの他の記事】
文・構成:浦島正裕(ジャズピアニスト/音楽理論講師)
ピアノと言葉を通して、日々、音楽の仕組みと心の動きの接点を探し続けています。
音楽の音にある「理由」を、常に多角的に考えています。
☆『THE PALM OF A BEAR』/浦島正裕
【クリエイティブノート】この連載は1992年にMusician Magazineに掲載されたTony Schermanによるインタビューを参考にし、独自の再構成と解釈を加えたフィクション形式の記事です。実在の発言内容を基にしていますが、構成上の演出や編集が含まれます。ジャズを学ぶ読者の学習と創造力を促す目的で制作しています。