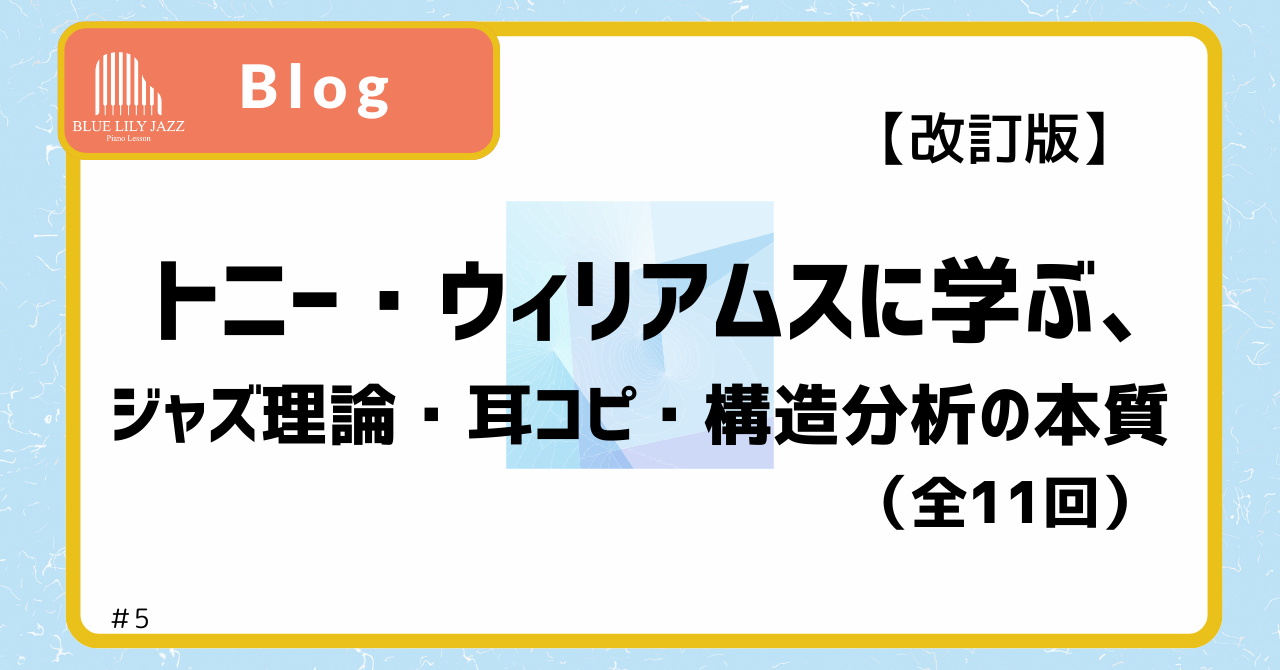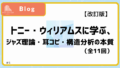第9回:トニー・ウィリアムスのエレクトリックバンド再考|ジャズとロックの融合
トニー・ウィリアムスが「現代のジャズ」を描こうとした場所
クインテットの陰で、密かに始まったもうひとつの実験
インタビュアー:トニー、あなたが80年代に復活させたアコースティック・クインテットは、王道として大きな評価を得ました。
でもその一方で、同時期に“エレクトリックバンド”の構想を持っていたと聞きました。
トニー:ああ、それは本当だよ。クインテットとは別に、もう少し自由なサウンドを探していた。
ギター、キーボード、エレクトリック・ベース、サックス、そしてドラム――その編成で、アコースティックとエレクトリックの“橋渡し”をしたかったんだ。
インタビュアー:それは、70年代のLifetimeの延長というより、新しい構想だった?
トニー:まったく別物さ。Lifetimeはエレクトリックでも“ジャズ・ロック”寄りだったけど、
今回目指したのは「コード進行を保ったまま、音色で揺らぐ」音楽だった。
構造はしっかりしてるけど、音像はモヤッとしてる。そういう矛盾を抱えた音楽がやりたかった。
☆トニーから学べること☆
きっと彼にとって“新しい音”とは、極端な革新ではなく、“ジャンルの間”にあるあいまいな領域だったんでしょうね。
その「あいまいさ」を設計するためには、確かな構造と理論が必要だというのも、彼らしい発想です。
☆トニーのエレクトリックバンドを聴くならこれ!①
エマージェンシー!【Amazonで聴く】
Believe It【Amazonで聴く】
音色はもうひとつのリズムである
インタビュアー:このエレクトリックバンドでは、あなたのドラミングもやや異なって聴こえました。
より広く、タッチも軽やかに感じました。
トニー:それは音のテクスチャーを意識してたからだよ。
アコースティックのクインテットでは、アタックやグルーヴの“芯”が必要だったけど、
エレクトリックでは、“音の色”で会話するような感覚が求められる。
つまり、リズムではなく「質感」がリズムの代わりになるんだ。
インタビュアー:音色そのものが、“時間の流れ”をつくる?
トニー:そう。たとえば、ブラシで叩いたスネアにディレイをかけると、
それだけで「時間の奥行き」が生まれる。それをベースが引き取って、キーボードが空間を伸ばす――
その一つひとつが時間の別の層を作るんだよ。
☆トニーから学べること☆
“リズム”とは拍を刻むだけではなく、“質感の変化”としても存在する。
彼は、音の「揺らぎ」「余白」「色合い」にリズム的な価値を見出していた。
これは、現代音楽的な感覚でもあり、即興演奏にも応用できる視点ですね。
☆トニーのエレクトリックバンドを聴くならこれ!②
エゴ 【Amazonで聴く】
Turn It Over/lifetime【Amazonで聴く】
形式より「鳴り方」で聴かせる音楽
インタビュアー:このエレクトリックバンドでは、コード進行自体は割とトラディショナルなものが多いですね。
それでも「新しく聴こえる」のは、何が理由でしょう?
トニー:鳴らし方だね。
コードはⅢ-Ⅵ-Ⅱ-Ⅴみたいな動きでも、テンションの乗せ方や音域の選び方で空気が変わる。
それに、ギターやキーボードの“ヴォイシングの隙間”をどう取るかも大事。
たとえば、C△7を弾いても、ベースはAを弾いて、上に♯11を足して浮遊感を出す。
コードネームは変わらなくても、聴こえ方が全然違うんだよ。
インタビュアー:つまり、「構造の上に、響きで嘘をつく」ような感覚?
トニー:嘘じゃないけど(笑)、“多義的にする”って感じかな。
ひとつのコードに、いくつもの意味を持たせる。
演奏者によって、同じ譜面でもまったく違う景色が出せる――そういう曲が好きだったんだ。
☆トニーから学べること☆
「どんなコードを書くか」以上に、「どう響かせるか」を大事にする。
これは、作曲にも演奏にも通じる本質的な姿勢ですね。
構造を明確にしつつ、音の“あいまいさ”を楽しむ――そのバランスが、現代的なジャズ表現の鍵なのかもしれません。
☆音楽の構造とともに響きを深く知るための理論書☆
▶ 構造的思考と響きを深めたいあなたに:
・『ジャズにおける作曲の理論と実践 ジャズ・コンポジション』(Amazonで詳しく見る)
・ハーモニーに新しいカラーを加える リハーモナイゼーション・テクニック エクササイズと模範解答付(Amazonで詳しく見る)
※これら本では、作曲・リハーモナイズ・アレンジの発想法が学べます。リディアン的なトライアド配置や、モーダルな進行の中での“構造保持”に悩んでいる人に特におすすめです。
設計図は緩やかに、表現は具体的に
インタビュアー:この電気バンドの譜面には、どれくらい細かく指定があったんですか?
トニー:構造はきっちり書いた。でも、演奏指示は意図的に少なめにした。
“このコードの意味”を感じ取って、自分のタッチで表現してほしかったから。
たとえば、「ここは柔らかく」とか「沈む感じで」とか、そういう言葉の方が多かったかも。
インタビュアー:それは、演奏者の解釈力に委ねるという意味でもありますね。
トニー:そう。僕は、音楽家の「解釈力」を信用したかった。
だからこそ、スコアは“可能性の設計図”であって、完成形じゃないんだ。
それをどう鳴らすかは、演奏する人間の“今この瞬間の感性”に任せたかった。
☆トニーから学べること☆
「全てを決めない勇気」が、創造の幅を広げる。
構造を整えつつも、演奏者に“余白”を与えること――
それが、音楽を“生きているもの”にする力になるのだと、トニーは教えてくれている気がします。
☆トニーのエレクトリックバンドを聴くならこれ!③
The Joy of Flying【Amazonで聴く】
The Million Dollar Legs【Amazonで聴く】
次回予告:第10回:トニー・ウィリアムスに学ぶ模倣と創造の本質|自由と構造のバランスを掘り下げる【前編
音楽と人生を貫いた“自分であろうとする”強さ
第10回では、ドラマー、作曲家、思想家としてのトニー・ウィリアムスの姿を総括していきます。
彼が生涯をかけて模索した「音楽で自分を語ること」とは何だったのか?
模倣から始まり、構築へ向かったその歩みの先に見えた、“音楽家の肖像”を描き出します。
文・構成:浦島正裕(ジャズピアニスト/音楽理論講師)
ピアノと言葉を通して、日々、音楽の仕組みと心の動きの接点を探し続けています。
音楽の音にある「理由」を、常に多角的に考えています。
☆『THE PALM OF A BEAR』/浦島正裕
【クリエイティブノート】この連載は1992年にMusician Magazineに掲載されたTony Schermanによるインタビューを参考にし、独自の再構成と解釈を加えたフィクション形式の記事です。実在の発言内容を基にしていますが、構成上の演出や編集が含まれます。ジャズを学ぶ読者の学習と創造力を促す目的で制作しています。