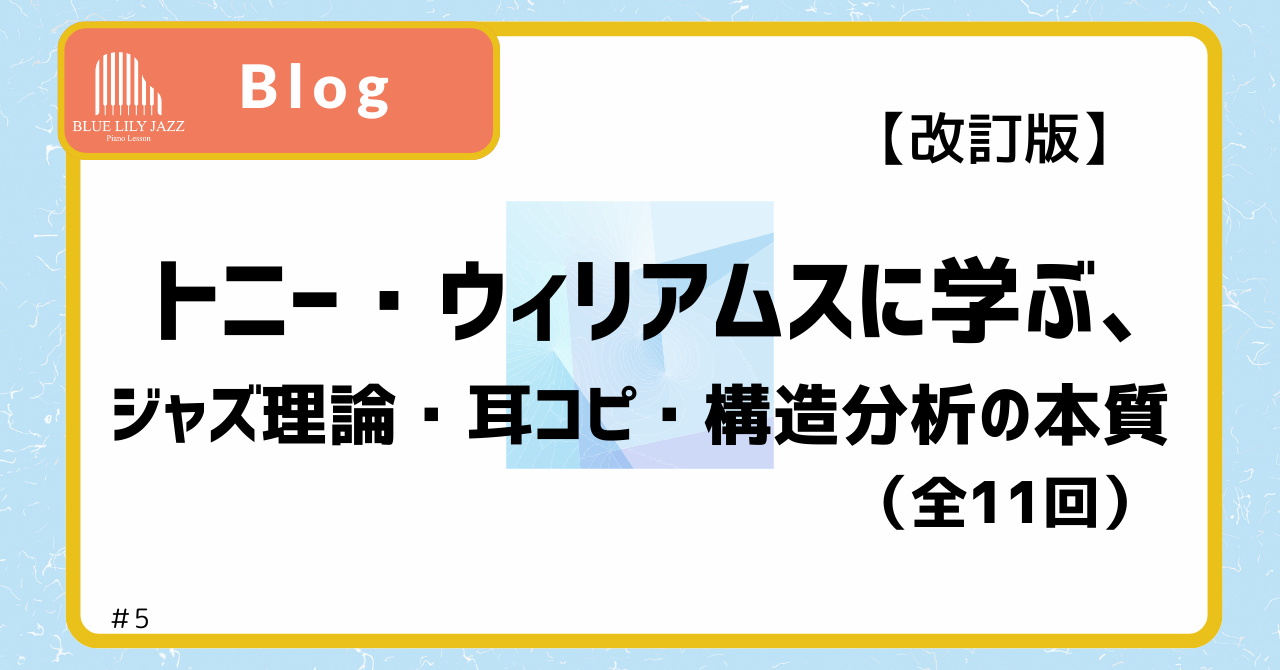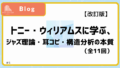第5回 旋律の設計図とベースラインの構造美|トニー・ウィリアムスの作曲技法 ― 「Sister Cheryl」
トニー・ウィリアムスが目指した、“聴く人に届く”ための音のデザイン
まずは聴いてみよう!トニーの構造的作曲への思いを体験できるアルバムです。⇒トニー・ウィリアムスの初リーダー作『Life Time』をAmazonで聴く
一音一音の配置に込めた「構築」の思想
インタビュアー:前回、『Sister Cheryl』の話で“歌えるメロディ”と“動くハーモニー”のバランスというテーマが出ました。
今回はもう少し踏み込んで、曲の構造について教えていただけますか?
トニー:もちろん。この曲はね、表面はとても歌いやすいんだけど、構造的にはかなり設計されたものなんだ。
最初のモチーフは、8小節で完結するシンプルなメロディ。でも、それをただ繰り返すんじゃなくて、「どうやって展開させるか」をずっと考えてた。
インタビュアー:具体的には、どんな工夫が?
トニー:たとえば、最初の4小節のメロディは第2声部と重ねて上下に動かせるように書いてる。
つまり、カウンターメロディを想定して、すでに空間が設計されてるんだ。
次に、9小節目からはあえてサブドミナントの代理和音を用いて、一度聴き手の注意をずらす。
そして、14〜15小節目でドミナントをしっかり鳴らして、16小節目でキレイに解決――
でも、実は完全には終わってない。“解決っぽく聴こえるけど、どこか浮いている”という感覚を残すようにしてる。
☆トニーから学べること☆
メロディの展開には「聴き手の感覚」と「音楽的構造」の両方が必要なんですね。
トニーは、ただ歌えるだけではなく、聴く人の感情の流れをコントロールする構造を意識していたんだと思います。
その「仕掛け」が曲の魅力になっているのかもしれません。
☆作曲に関する理論書☆
▶ トニーのように“構造”から音楽を構築するために:
・『ジャズにおける作曲の理論と実践 ジャズ・コンポジション』(Amazonで詳しく見る)
・ハーモニーに新しいカラーを加える リハーモナイゼーション・テクニック エクササイズと模範解答付(Amazonで詳しく見る)
※これら本では、作曲・リハーモナイズ・アレンジの発想法が学べます。リディアン的なトライアド配置や、モーダルな進行の中での“構造保持”に悩んでいる人に特におすすめです。
ベースラインが変える世界 ― 音の土台を“動かす”発想
インタビュアー:この曲のもうひとつの特徴は、ベースラインの巧妙な使い方ですね。
トニー:そうだね。ベースって、ただの低音じゃなくて、“和声全体の意味”を決めるんだよ。
たとえば、メロディはそのままにして、ベースだけを半音ずらすと、コード全体が違って聴こえる。
この曲では、ベースが次の和音の予告になったり、逆に“偽終止”を演出したりしてる。
インタビュアー:ベースラインが、コードを導く“ナレーター”の役割を果たしているような?
トニー:まさにその通り!
僕は、コード進行を固定するんじゃなくて、ベースの動きに合わせて“コードの重心”を動かすようにしたかった。
だからBメジャーから始まって、A♭マイナー7、Aメジャー、Bメジャーと進む間、実はB、C♯、F♯の3音だけはずっと保ってる。
これによって、聴感上は“変化してるのに繋がってる”っていう不思議な感覚が生まれる。
☆トニーから学べること☆
Aメジャー上でのBメジャートライアド(B、C♯、F♯)!リディアンのアッパーストラクチャーの響きですね!コード進行の中で上手く使われています。
音楽の“変化”は、メロディだけじゃなくて、ベースラインの設計によっても生み出せるんですね。
それによって、変化と統一感のバランスをコントロールできる。
トニーの発想は、まさに“構造家”としての視点そのものでした。
☆ベースラインを上手く組み立てたい人のための必読書!
・イージー・ジャズ・コンセプション ベース・ライン (はじめてのジャズ・エチュード) 【Amazonで見る】
・ロン・カーター ビルディング・ジャズ・ベース・ライン【Amazonで見る】
※この本では、ベースライン設計の考え方が学べます。ベースラインの組み立てに悩んでいる人に特におすすめです。
構築しながら「語らせる」ためのリズム
インタビュアー:この曲のリズムもユニークですよね。浮遊感がありつつ、すごく“語るよう”に聴こえる。
トニー:そこは特に意識した。僕の中で、リズムは“運動”じゃなくて“会話”なんだよ。
だから、メロディが「語る」ためのリズム的間合いが必要だった。
1拍休みをどこに入れるか、8分音符を“押し出す”のか“引っ込める”のか――全部、語尾のニュアンスと一緒。
インタビュアー:語尾……?
トニー:そう。たとえば、ジャズのバラードでシンガーがフレーズの終わりに少しだけ間を空けるだろ?
あれと同じことを、リズムの中でやりたかった。
ドラムのフィルでも、コードの伸ばしでも、“行間”をつくる。
それによって、聴き手が“あ、この曲は自分に何か話しかけてきてる”って感じてくれるようにしたかったんだ。
☆トニーから学べること☆
少し実技的な点からお話すると。間をつくるのは非常に難しい。具体的には、休符が多い曲はとても演奏し辛いものだったりします。しかし、会話において間が重要なように、音楽においても間は重要です。
きっと彼にとって、音楽は“情報”じゃなく“会話”だったんでしょう。
だからこそ、「語りかけるような」間合いやニュアンスをとても大切にしていた。
私たちも、演奏や作曲で“何を話すか”“どう話すか”を意識することが、
本当の意味で人に届く音楽を作る鍵になるのかもしれません。
☆ドラムのフィルだけではなく、歴史に残るジャズドラマーのリックがスコア付で説明されています!必読!
・ジャズドラム名演集 JAZZ DRUM FAMOUS PLAYING(Amazonで見る)
色々なジャズドラマーの特徴を知るには欠かせない本です!!
曲が「一人歩きする」ことの喜び
インタビュアー:この曲は、他のプレイヤーたちによってもよく演奏されますね。
それを聴いたとき、どう感じますか?
トニー:嬉しいに決まってるさ。
自分の曲が、自分の手を離れて“誰かの言葉”になる――これは音楽家として最高の瞬間のひとつだと思うよ。
インタビュアー:それは、作曲家としての喜び?
トニー:それだけじゃない。
「自分の中にあった感情や構造」が、他人の演奏で再現されるとき、その人の感情も重なって、新しい命が生まれるんだ。
『Sister Cheryl』がそんな風に“生き続ける存在”になってくれたなら、本当にありがたい。
☆トニーから学べること☆
きっと、彼は「音楽は個人のものだけではない」と信じていたんでしょう。
作曲することは、自分の感情を世界に解き放つ行為でもある。
そして、それが他人の表現として育っていくことで、自分の中の音楽が“普遍性”を獲得していく――
そんな、時間を超えた美しさがあるのだと思います。
☆オススメ理論書☆
▶ トニーのように“構造”から音楽を構築するために参考になる理論書:
・『マークレヴィン ザ・ジャズ・セオリー』(Amazonで見る)
※この本では、ジャズの構造や発想法が学べます。モードジャズなどでスケールの使い方に悩んでいる人に特におすすめです。
次回予告:Sister Cherylの作曲分析|トニー・ウィリアムスに学ぶ旋律とベースラインの構築
“打楽器奏者”を超えて、“音楽の建築家”になるまで
第6回では、トニー・ウィリアムスが作曲家として自分を確立していく過程を追います。
ストリングカルテットやフーガ、対位法といったクラシカルな技法を学びながら、
「即興だけでは足りない」と感じた彼が、“作品”として音楽を作ることの意味を模索する様子を深掘りしていきます。
【このシリーズの他の記事】
文・構成:浦島正裕(ジャズピアニスト/音楽理論講師)
ピアノと言葉を通して、日々、音楽の仕組みと心の動きの接点を探し続けています。
音楽の音にある「理由」を、常に多角的に考えています。
☆『THE PALM OF A BEAR』/浦島正裕
【クリエイティブノート】この連載は1992年にMusician Magazineに掲載されたTony Schermanによるインタビューを参考にし、独自の再構成と解釈を加えたフィクション形式の記事です。実在の発言内容を基にしていますが、構成上の演出や編集が含まれます。ジャズを学ぶ読者の学習と創造力を促す目的で制作しています。