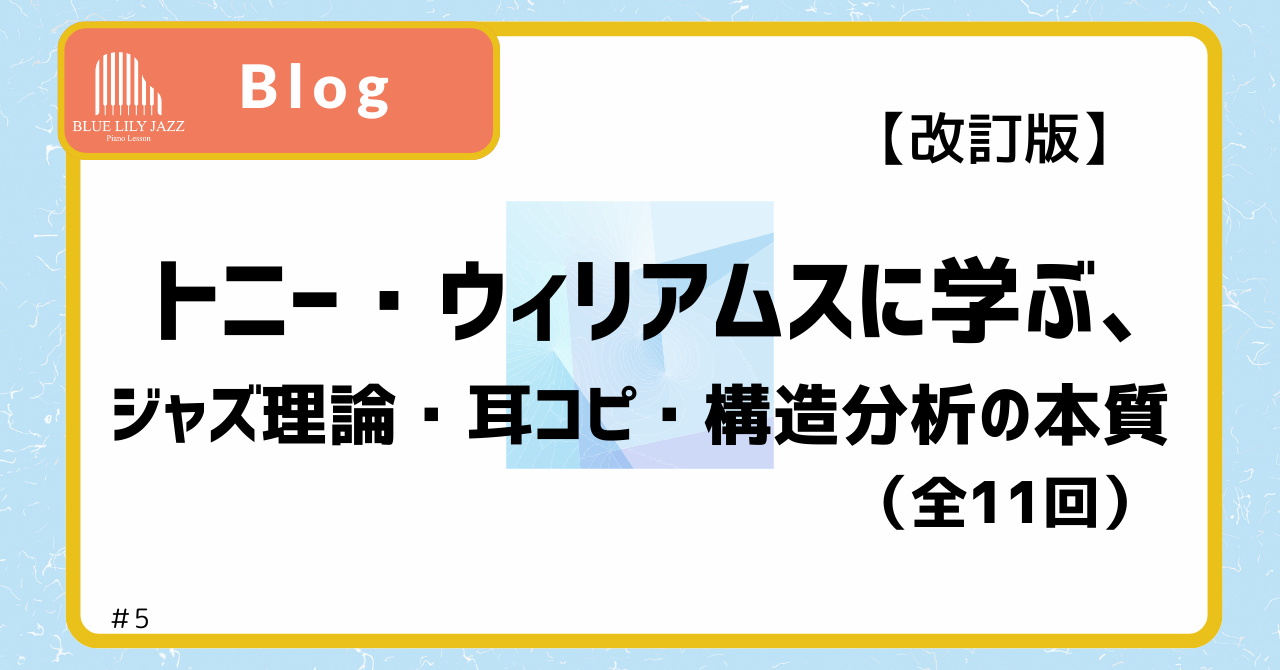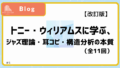第4回:Sister Cherylの秘密|トニー・ウィリアムスに学ぶ作曲とハーモニーの構造
トニー・ウィリアムス、歌えるメロディと複雑なハーモニーへの挑戦
曲作りの転機 ― 「Sister Cheryl」の誕生
まずは聴いてみよう!トニーの構造的作曲への思いを体験できるアルバムです。⇒トニー・ウィリアムスの初リーダー作『Life Time』をAmazonで聴く
インタビュアー:トニー、あなたはずっと“生の感覚”を大事にしてきたとおっしゃってましたが、名曲『Sister Cheryl』について教えてください。
この曲は、これまでの模倣から一歩進んで「誰もが口ずさめる」メロディと、複雑さを併せ持ったコード進行が特徴だと聞きますが。
トニー:そうだね。『Sister Cheryl』は、以前から「誰でも歌えるメロディがほしい」という思いがあったんだ。
もちろん、僕の初期の作曲は、純粋に感覚に従って構築していた。でも、ある時ふと「これだと、もっと多くの人に伝わるんじゃないか?」って考えた。
だから、今回はシンプルなメロディに、同時に高次なハーモニー―具体的には、サブドミナントの役割を極めたコード進行を取り入れたんだ。
インタビュアー:具体的な例を挙げると?
トニー:たとえば、冒頭のフレーズはBメジャーで始まる。普通ならBメジャーの3度を使うところを、あえて2度中心に置いてみた。
B、C♯、F♯というシンプルな構成だけど、そのシンプルさが逆に柔軟性を持たせ、どんなコードにも対応できるように工夫してる。
そして、続く部分で、A♭マイナー7への転換を導入。最初のBメジャーの要素を保ちつつも、ハーモニー全体に新しい色彩をもたらすようにしたんだ。
これが、僕の狙いだったんだよ。
☆トニーから学べること☆
きっと、トニーは「単純さの中に奥深さが宿る」ことに気づいていたんですね。
たとえシンプルなメロディでも、どの音がどんなハーモニーと結びつくか、その関係性を深く考えることで、音楽は驚くほど豊かになるのだと感じられます。
更にダイアトニック・コードの機能を上手に作曲に取り入れているところは、基本を大切にするという点において注目すべきどころです。
☆作曲に関する理論書☆
▶ トニーのように“構造”から音楽を構築するために:
・『ジャズにおける作曲の理論と実践 ジャズ・コンポジション』(Amazonで詳しく見る)
※この本では、リハーモナイズやアレンジの発想法が学べます。リディアン的なトライアド配置や、モーダルな進行の中での“構造保持”に悩んでいる人に特におすすめです。
ハーモニーとメロディ ― ハーモニーの設計と思考|感覚と理論の交差点
インタビュアー:『Sister Cheryl』は、ただキャッチーなだけでなく、複雑なハーモニーが特徴とおっしゃいましたね。
それをどのように設計したのですか?
トニー:僕が目指したのは、メロディが自然に歌われる一方で、コードの展開に独自性があること。
例えば、ベースラインを動かすだけで、コード全体が変わるような仕組みを取り入れたんだ。
最初のBメジャーの中に残したB、C♯、F♯という核があり、そこからベースを変えるだけで、A♭マイナー7やその他の和音が成立するように構成してる。
こうすることで、メロディは一貫しているが、ハーモニーは常に動きがあって、聴く側に「何かが変わる」というワクワク感を与えられると考えた。
インタビュアー:なるほど。理論的には、対位法やモーダルな要素も活かされたのですね。
トニー:そうだ。後から理論を学んでから、あのフレーズがなぜ機能していたかが、ようやく言葉で説明できるようになった。
たとえば、サブドミナントの導入は、コード進行に遅延感と温かみを与える。これにより、メロディの「呼吸」が生まれるんだ。
その理論的根拠をしっかり理解することで、単なる直感ではなく、計算された美しさも感じられるようになった。
☆トニーから学べること☆
おそらく、トニーは「感覚と理論は相反するものではなく、むしろ補完し合う」ということを実感していたのだと思います。
耳で感じたものに、後から理論という名称を与えることで、自分の表現を明確にできる。
私たちも、感じることと理論的に説明すること、この両輪を大切にしたいですね。
☆オススメ理論書☆
▶ トニーのように“構造”から音楽を構築するために参考になる理論書:
・『マークレヴィン ザ・ジャズ・セオリー』(Amazonで見る)
※この本では、ジャズの構造や発想法が学べます。モードジャズなどでスケールの使い方に悩んでいる人に特におすすめです。
自己表現のための作曲 ― ジャズ作曲とは何か|トニーが語る“創造”の本質
インタビュアー:『Sister Cheryl』を生み出した背景には、「誰もが口ずさめる」音楽への憧れがあったとおっしゃっていましたが…。
トニー:そうだね。僕はずっと「ただのドラマー」ではなく、「音楽家として自分を表現できる存在」になりたかった。
演奏だけでは、たしかにそのときの感情は伝わる。でも、作曲することで、
自分の意志や思いを、構造という形で固めることができる。
その結果、他のミュージシャンがその曲を演奏する時、「これはトニーが生み出したものだ」と分かる、そんな普遍性を目指した。
インタビュアー:つまり、作曲は自分を超えて、伝えたいメッセージを具現化する手段なのですね。
トニー:まさに。楽曲は生きた言葉で、演奏されるたびに新たな命を吹き込まれる。
『Sister Cheryl』も、その一例で、僕が感じた「誰にでも届くメロディ」と「音楽的革新」を結合したものなんだ。
☆トニーから学べること☆
きっと彼は、「自分の内側にあるものは、外に出してこそ価値がある」と感じたんでしょう。
作曲するという行為は、ただの試行錯誤ではなく、自己表現の究極の形として、
自分が何者であるかを音で伝える大切なプロセスだと思います。
次回予告:第5回 旋律の設計図 ― 「Sister Cheryl」の奥にある構築美
【Sister Cheryl】の先に見えた、誰もが触れ合える音楽表現!
第5回では、『Sister Cheryl』のさらなるディテールに迫ります。
その構成、転調、リズムの変化、そして歌えるメロディがどのように生み出されたのか。
トニー自身がどのような試行錯誤を経て、普遍的な楽曲を作り上げたのかを、
より深く掘り下げ、分析します。
次回もお楽しみに!
名曲『Sister Cheryl』聴いてみよう!⇒トニー・ウィリアムスの初リーダー作『Life Time』をAmazonで聴く
【このシリーズの他の記事】
文・構成:浦島正裕(ジャズピアニスト/音楽理論講師)
ピアノと言葉を通して、日々、音楽の仕組みと心の動きの接点を探し続けています。
音楽の音にある「理由」を、常に多角的に考えています。
☆『THE PALM OF A BEAR』/浦島正裕
【クリエイティブノート】この連載は1992年にMusician Magazineに掲載されたTony Schermanによるインタビューを参考にし、独自の再構成と解釈を加えたフィクション形式の記事です。実在の発言内容を基にしていますが、構成上の演出や編集が含まれます。ジャズを学ぶ読者の学習と創造力を促す目的で制作しています。