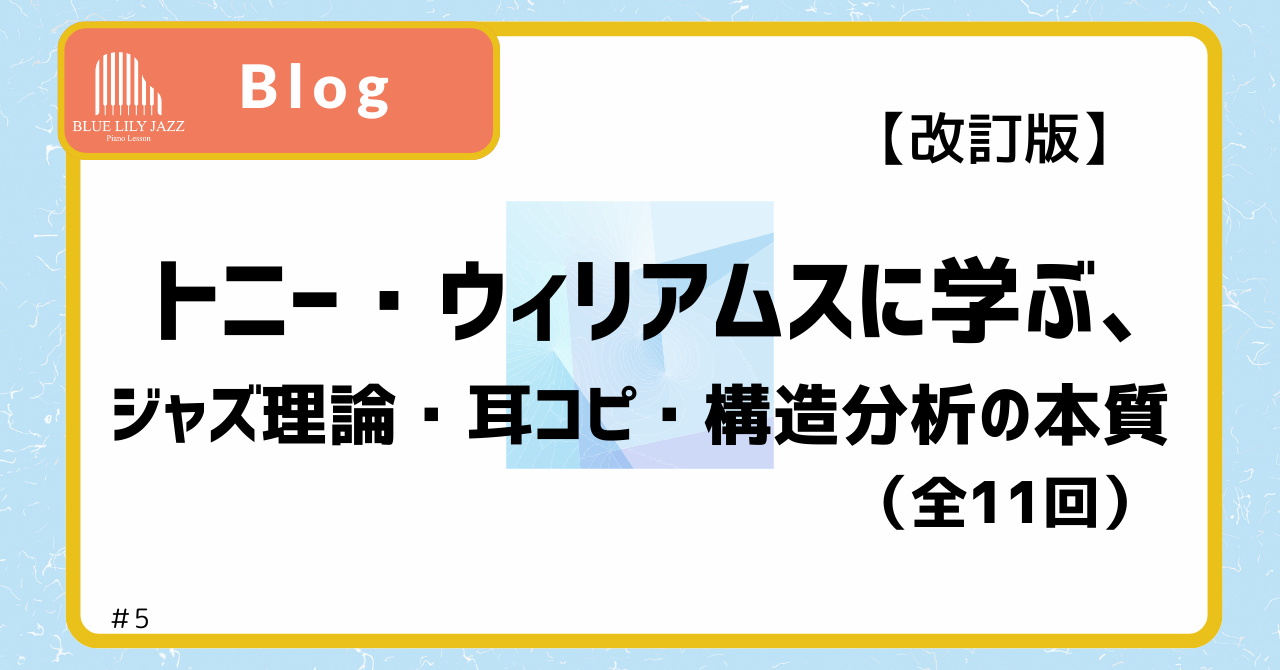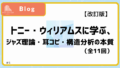第6回:Sister Cherylの作曲分析|トニー・ウィリアムスに学ぶ旋律とベースラインの構築
トニー・ウィリアムスが「音楽の建築家」へと変貌していく瞬間
ドラムだけでは足りない
インタビュアー:トニー、あなたは演奏だけではなく、作曲にものめり込んでいきましたね。
その理由は何だったんでしょう?
トニー:単純に言えば、「足りなかった」んだよ。
ドラムはずっと好きだし、いまでも楽しい。でもね、ある時から「これだけじゃ表現できないことがある」と思うようになった。
演奏は即興的で、瞬間の反応が求められる。けれど、もっと時間をかけて、考えて、組み立てることがしたくなったんだ。
インタビュアー:それが“作曲”という形で現れた。
トニー:そう。構築という意味では、ドラムも同じだけど、作曲はより長いスパンで考えられる。
「この8小節があるから、次の16小節がこう動く」というように、音楽の全体像を設計する感覚がある。
それを味わってしまったら、もう戻れなかった。
☆トニーから学べること☆
演奏とは異なる表現の欲求が生まれたとき、「作る」という選択肢が生まれるんですね。
即興の反射神経だけでは足りない、もっと長い言葉で語りたい――
そんな想いが、トニーを作曲へと導いたのだと思います。
☆作曲に関する理論書☆
▶ トニーのように“構造”から音楽を構築するために:
・『ジャズにおける作曲の理論と実践 ジャズ・コンポジション』(Amazonで詳しく見る)
・ハーモニーに新しいカラーを加える リハーモナイゼーション・テクニック エクササイズと模範解答付(Amazonで詳しく見る)
※これら本では、作曲・リハーモナイズ・アレンジの発想法が学べます。リディアン的なトライアド配置や、モーダルな進行の中での“構造保持”に悩んでいる人に特におすすめです。
ベートーヴェンとモーツァルトに“学び直す”
インタビュアー:作曲を学ぶために、クラシックの勉強も本格的に始めたそうですね。
トニー:ああ。1979年ごろ、サンフランシスコに移ってから、ロバート・グリーンバーグという作曲家に師事した。
彼との勉強は、まるで大学に通ってるみたいだったよ。
まず種々の対位法――カノン、インヴァーテッド・カウンターポイント、フーガ。
それから、ミニュエットとトリオ、ロンド、主題と変奏……
ベートーヴェンやブラームスを分析しながら、「構造の意味」を徹底的に学んだんだ。
インタビュアー:ジャズの世界から見ると、かなり遠いところですよね。
トニー:でも、根っこは同じなんだよ。どのジャンルでも、音楽って「動きと展開」からできてる。
クラシックを学んだからこそ、自分の中の音楽的な設計力が鍛えられたと思う。
モーツァルトが第2主題をどこに置くか、ベートーヴェンが主題をどう崩していくか――それを理解することで、僕の作曲も深くなった。
☆トニーから学べること☆
おそらく彼は、「自分のルーツにない音楽からも学べる」と信じていたのでしょう。
ジャズをやるからといって、ジャズだけを聴く必要はない。
異なるジャンルの構造や語法を取り入れることが、むしろ新しい表現の扉を開いてくれるのだと感じます。
☆オススメ理論書☆
▶ トニーのように“対位法”を勉強する人のために:
・対位法/矢代秋雄(訳)(Amazonで見る)
“感覚”を“構造”にする知性
インタビュアー:クラシックの対位法って、ルールが厳しそうですよね。即興とは対極のようにも思えます。
トニー:たしかにそうだけど、それが逆に面白かったんだ。
即興では“感じたもの”をその場で出す。でも、対位法では「この音を動かすには、どういうルールを守るか」がある。
ルールの中で最大限自由になる感覚って、ドラムにも通じるところがあった。
インタビュアー:それは、ジャズにどう応用できたんですか?
トニー:たとえば、テーマを提示した後、どうやって展開するか。
変奏するのか、反転させるのか、リズムを伸ばすのか――そういう発想が自然に浮かぶようになった。
それに、演奏中でも「このモチーフを少し変形して繰り返せば、聴き手は理解しやすいな」とか、
構造を意識した演奏ができるようになったんだ。
☆トニーから学べること☆
“感覚の人”と思われがちなトニーも、その感覚を支える知性と分析力を持っていたんですね。
感じたものをどう整理し、展開し、再提示するか――
それを知ることで、即興演奏も“構築された語り”に変わっていくのだと感じます。
そう言えば、同じジャズドラマーのピーター・アースキンが、何かのインタビューで「今何を学びたいか?」と聞かれて、「対位法!」と答えていました。トニーの影響かもしれません。
☆ドラムをしっかりと学びたい人にはこれ!ピーター・アースキンの教則本!
アースキンメソッドフォードラムセット(日本語字幕入り 2DVD付) (Amazonで見る)
作品は「考え抜いた即興」である
インタビュアー:クラシックの勉強とジャズの即興って、矛盾しているようにも思えます。
トニー:そう思うかい? 僕は逆だと思う。
ジャズのソロだって、良い演奏は全部“構造を持っている”。
イントロでモチーフを提示して、ミドルで展開して、アウトロで回収する――それってまさにソナタ形式じゃないか?
インタビュアー:なるほど、即興にも構造がある。
トニー:演奏中のひらめきにも、無意識のうちに学んだ構築感覚が流れ込むんだ。
だからこそ、作曲を学ぶ意味は大きい。
ただの“かっこいいリック”を並べるんじゃなく、聴き手が“旅をした気分”になるような展開がつくれる。
それが、僕にとっての“作品”なんだよ。
☆トニーから学べること☆
良い演奏は全部“構造を持っている”・・・という言葉はとても重みのある言葉だと思います。音楽を構造で聴いていくと新たな発見があるかもしれません。音楽には構造があるという点においてクラシックとジャズには共通しているところがあるんですね。
☆オススメ理論書☆
▶ トニーのように“構造”から音楽を構築するために参考になる理論書:
・『マークレヴィン ザ・ジャズ・セオリー』(Amazonで見る)
※この本では、ジャズの構造や発想法が学べます。モードジャズなどでスケールの使い方に悩んでいる人に特におすすめです。
次回予告:第7回 リチュアルという名の交響詩
ピアノと弦楽四重奏、打楽器が交差する15分間の創作
第7回では、トニーが初めて取り組んだ本格的な室内楽作品『Rituals』に迫ります。
ピアノ、ストリングカルテット、そして自らのドラムによる15分の組曲が、どのように構築され、どんな音世界を描いたのか。
“打楽器奏者”という枠を超え、“音の建築家”としてのトニーが見据えたものとは?
次回もお楽しみに!
【このシリーズの他の記事】
文・構成:浦島正裕(ジャズピアニスト/音楽理論講師)
ピアノと言葉を通して、日々、音楽の仕組みと心の動きの接点を探し続けています。
音楽の音にある「理由」を、常に多角的に考えています。
☆『THE PALM OF A BEAR』/浦島正裕
【クリエイティブノート】この連載は1992年にMusician Magazineに掲載されたTony Schermanによるインタビューを参考にし、独自の再構成と解釈を加えたフィクション形式の記事です。実在の発言内容を基にしていますが、構成上の演出や編集が含まれます。ジャズを学ぶ読者の学習と創造力を促す目的で制作しています。