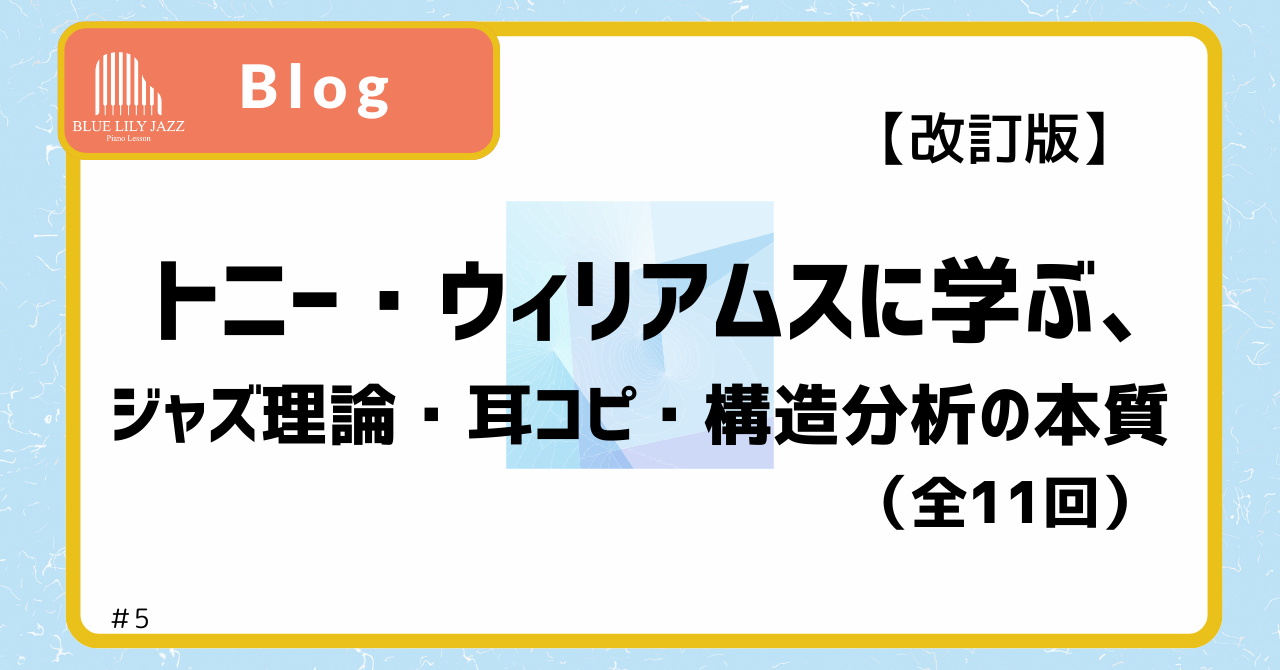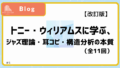第8回:トニー・ウィリアムスのジャズ・クインテット再生|即興と構造の融合
トニー・ウィリアムス、“今”の中に“古さ”を響かせる理由
誰もやっていないことを、もう一度やる
インタビュアー:トニー、1986年にあなたが再びアコースティックのジャズ・クインテットを始めたことは、多くの人にとって意外な選択だったと思います。
当時はエレクトリックやフュージョンの波が主流でしたから。
トニー:それが理由だったんだ。
みんなが“新しさ”を追っている中で、僕は“古さの中にある未完成”をもう一度掘り下げたくなった。
そして、ジャズ・クインテットというフォーマットは、どんな編成よりも会話ができる場なんだよ。
2管+リズムセクション――これは、僕にとって“音楽の最小単位”だった。
インタビュアー:だから、あえてそこに戻った?
トニー:戻るというより、「再発明」だね。
同じフォーマットでも、音楽の内容をすべて変えれば、それは“今”の音楽になる。
そして誰もやってなかった。“王道”が空席だったから、僕はそこに座っただけだよ。
☆トニーから学べること☆
彼は“新しさ”を作るとは、必ずしも形を変えることではなく、“精神の更新”だと理解していたんですね。
形式に頼らず、中身をどう刷新するか――そこに本当の革新があるのかもしれません。
☆「Native Heart」はトニーの作曲家としての側面が全面に出た作品であり、ハード・バップと現代的な構造が融合した意欲作!必聴!
Native Heart(Amazonで聴く)
自作曲だけで固めるという覚悟
インタビュアー:このクインテットでは、全曲あなたのオリジナルですね。
スタンダードを演奏しないというのは、当時としては珍しい選択でした。
トニー:そうかもしれない。でも、僕にとっては自然な流れだった。
「自分の言葉で話す」ことが、このバンドの目的だったから。
スタンダードには敬意を持っているけど、それを演奏するためのグループじゃなかった。
メンバーひとりひとりが、“新しい会話”を交わせる場にしたかったんだ。
インタビュアー:作曲は全体のコンセプトから考えていた?
トニー:もちろん。1曲ごとに“場面”や“感情”を設計した。
リズム構造やハーモニー進行だけじゃなく、ソロの展開をどう導くかも譜面に落とし込んだ。
自由な即興の中にも、「こう進んで、こう跳ね返る」という道筋を想定してた。
☆トニーから学べること☆
「自由であるためには、構造が必要」という彼の姿勢は、即興演奏にも共通しますね。
決められた枠の中でこそ、思考が深まり、表現が生まれる。
これは作曲でも、アンサンブルでも、学びとしてとても大切なことです。
☆作曲に関する理論書☆
▶ 作曲と構造的思考を深めたいあなたに:
・『ジャズにおける作曲の理論と実践 ジャズ・コンポジション』(Amazonで詳しく見る)
・ハーモニーに新しいカラーを加える リハーモナイゼーション・テクニック エクササイズと模範解答付(Amazonで詳しく見る)
※これら本では、作曲・リハーモナイズ・アレンジの発想法が学べます。リディアン的なトライアド配置や、モーダルな進行の中での“構造保持”に悩んでいる人に特におすすめです。
“リズムの言葉”で物語を紡ぐ
インタビュアー:このクインテットは、“モダンジャズ再生”という言い方をされることもあります。
ご自身では、どのように受け止めていましたか?
トニー:再生? いや、僕はそんなつもりはなかったよ(笑)。
伝統をなぞるのではなく、問い直していたんだ。
「クインテットって、なぜ2管なんだろう?」「なぜテーマとソロという構造なんだろう?」――
そうやって問い直して、答えを“自分の方法”で出したかった。
インタビュアー:過去を批判するのではなく、“選び直す”という姿勢ですね。
トニー:そう。ジャズは進化していく音楽なんだ。
そして、進化とは「新しくすること」じゃなく、「本当に必要なものを選び直すこと」なんだよ。
それができれば、過去の形式でも、ちゃんと“今”の音がする。
☆トニーから学べること☆
伝統とは守るものではなく、“再解釈するもの”。
彼のように「問い直す」ことが、表現を生きたものにしていく――
それは、音楽に限らず、あらゆる学びに通じる態度だと感じます。
☆この時代のトニーのピアノトリオのアルバム!マルグリュー・ミラー(P)の良さも堪能できる名盤です!
ヤング・アット・ハート(Amazonで聴く)
次回予告:第9回 トニー・ウィリアムスのエレクトリックバンド再考|ジャズとロックの融合
アコースティックとエレクトリックの狭間で、もうひとつの声を探す
第9回では、トニー・ウィリアムスが1980年代末から模索した“電気バンド”の構想に迫ります。
ギター、キーボード、サックス、ベースという編成で、彼が描こうとしたサウンドとは?
クインテットと並行して探った、“ジャンル横断型の現代ジャズ”の可能性を追います。
【このシリーズの他の記事】
文・構成:浦島正裕(ジャズピアニスト/音楽理論講師)
ピアノと言葉を通して、日々、音楽の仕組みと心の動きの接点を探し続けています。
音楽の音にある「理由」を、常に多角的に考えています。
☆『THE PALM OF A BEAR』/浦島正裕
【クリエイティブノート】この連載は1992年にMusician Magazineに掲載されたTony Schermanによるインタビューを参考にし、独自の再構成と解釈を加えたフィクション形式の記事です。実在の発言内容を基にしていますが、構成上の演出や編集が含まれます。ジャズを学ぶ読者の学習と創造力を促す目的で制作しています。