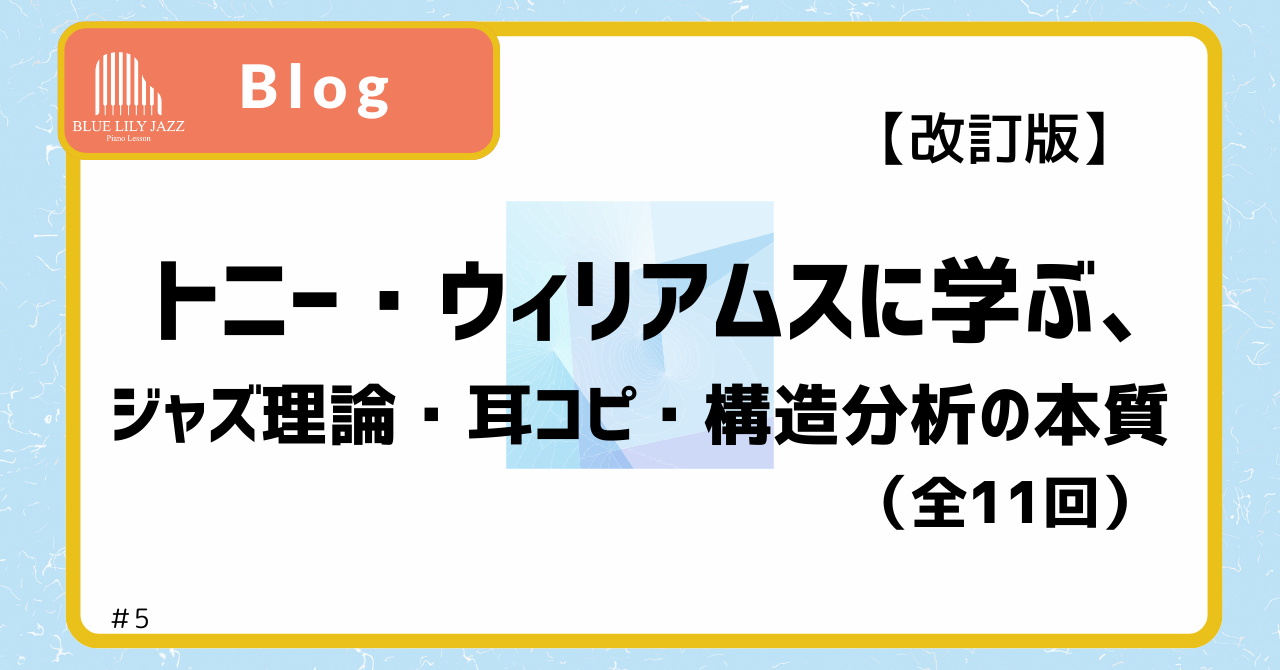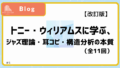第7回:トニー・ウィリアムスの『Rituals』を探る|ジャズとクラシックの融合
トニー・ウィリアムスが描いた“音楽の儀式”と創造の交差点
スウィングを超えて――打楽器奏者の再定義
インタビュアー:トニー、1980年代後半に入ってから、あなたはジャズの枠を超えた創作を多く手がけるようになりました。
なかでも『Rituals』は、ピアノ、弦楽四重奏、そしてドラムという異色の組み合わせでしたね。
トニー:そうだね。あれは本当に特別な体験だった。
あの曲では、僕は“ドラマー”というより、音楽を構築する建築家のような立場でいたかったんだ。
リズムだけじゃなく、空間、動き、そして沈黙までをも設計したかった。
インタビュアー:つまり、ドラムが主役ではなく、“音の一部”として存在するという発想ですか?
トニー:まさにそれ。ドラムって、どうしても“前に出る”楽器にされがちだけど、
僕にとっては“空間を区切る線”だったり、“感情の温度”だったりするんだよ。
「Rituals」では、その空間にピアノとストリングスを呼び込んで、音の儀式を作ろうとした。
(※トニー・ウィリアムスが作曲した「Rituals: Music for Piano, String Quartet, Drums and Cymbals」は、1990年にサンフランシスコのハーブスト・シアターで初演されました。この作品は、クロノス・カルテット、ハービー・ハンコック、そしてウィリアムス自身によって演奏されました。しかし、商業的な音源としてのリリースは確認されておらず、一般的な音楽配信サービスやCDでは入手できないようです。)
☆トニーから学べること☆
トニーは、ドラムを“演奏する道具”ではなく、“空間を設計するためのツール”と捉えていたのかもしれません。
自分の楽器の可能性を再定義する――それこそが創造的な音楽家の第一歩なのだと感じます。
☆ブラス・ストリングスのアレンジを学びたい人はこれ!とてもやさしく学べます!
・ブラス&ストリングス・アレンジ自由自在 完全版(Amazonで見る)
・楽器の重ね方がイチからわかる! 実践! やさしく学べる オーケストラアレンジ(Amazonで見る)
15分間の構造、ストーリーとしての音楽
インタビュアー:この曲は15分にもおよぶ長編作品ですね。どうやって構成されたのですか?
トニー:基本構成は三部構成。でも、それぞれのパートの中にも内部対比を作っている。
たとえば、第1部は静かなテーマの提示。旋律はピアノとチェロで提示され、弦がゆっくりと絡み合っていく。
第2部では、ポリリズムを使ってリズムの混乱を描き出す。ここで初めてドラムが前面に出てくる。
そして第3部では、再び静けさに戻り、最初のモチーフを変奏として再提示する。
インタビュアー:まるで交響詩のような構造ですね。
トニー:それを狙ったんだ。“物語としての音楽”を作りたかった。
テーマが登場し、それが成長し、混乱を経て、少し違う形で戻ってくる――
聴いてる人が“旅をしてきた”と思えるような構造にしたかった。
☆トニーから学べること☆
即興だけがジャズの本質ではないように、「ストーリーを語る構造」こそが音楽の芯である、という発想にハッとさせられます。
モチーフをどう展開し、どう回帰させるか――
それはまさに作曲の「文法」であり、表現の深みを決定づける技術です。
☆作曲に関する理論書☆
▶ トニーのように“構造”から音楽を構築するために:
・『ジャズにおける作曲の理論と実践 ジャズ・コンポジション』(Amazonで詳しく見る)
・ハーモニーに新しいカラーを加える リハーモナイゼーション・テクニック エクササイズと模範解答付(Amazonで詳しく見る)
※これら本では、作曲・リハーモナイズ・アレンジの発想法が学べます。リディアン的なトライアド配置や、モーダルな進行の中での“構造保持”に悩んでいる人に特におすすめです。
ジャンルの境界線は“考えた時点”で消える
インタビュアー:この曲では、クラシックのアプローチと、ジャズの即興性が融合しているように感じました。
あなた自身は、ジャンルの意識はありましたか?
トニー:いや、ほとんどなかったね。
強いて言えば、「いい音楽をつくりたい」って気持ちしかなかった。
ジャンルっていうのは、商業的な理由や外側からのラベルであって、
作ってる最中は“必要ない言葉”だと思う。
インタビュアー:では、どのように各セクションをつないだんですか?
トニー:音色、ダイナミクス、テンションとリリース――それらを頼りに、場面を移していった。
構造としては対位法をベースにした部分もあるし、リズムの遅延や重なりもクラシック的な発想から来てる。
でも、和声感は完全に僕のジャズ耳で作ってる。
つまり、ジャンルというより「自分の内側にあるすべて」が音になっただけなんだ。
☆トニーから学べること☆
ジャンルに縛られず、“音”そのものと向き合う――
トニーのこの姿勢から、「何をやるべきか」よりも「何を聴いているか」が大事なんだと気づかされます。
ジャンルを超えた音楽は、外側から目指すのではなく、内側から自然ににじみ出るものなのかもしれません。
音楽家として、“構築する者”でありたい
インタビュアー:この作品を通じて、あなたは「ドラマー以上の存在」になったと感じます。
ご自身では、どう捉えていましたか?
トニー:僕は、自分を「プレイヤー」ではなく、「構築する者」だと思いたいんだ。
もちろん、ドラムはずっと僕の“話す声”ではあるけど、それだけじゃ足りない。
僕の中には“構造を作りたい”という欲求がある。それが、作曲だったり、バンドを編成することだったり、
あるいは、こういう室内楽に挑戦することにつながってる。
インタビュアー:構築とは、具体的にどんなことですか?
トニー:全体の長さを決め、展開を考え、音色と強弱を配置し、聴く人が旅をできる音楽を作ること。
それができたとき、初めて“音楽を作った”って言える気がする。
即興だって、良いソロはみんな構造がある。
だから僕にとって「Rituals」は、自分の“音楽家としてのあり方”をはっきり示す作品だった。
☆トニーから学べること☆
音楽家とは、演奏する人ではなく、「世界を作る人」なのかもしれません。
トニーのように、音を積み重ねて空間を作り、時間を設計し、人を旅に連れていく。
そんな“構築”の感覚こそ、音楽に携わる者が磨き続けたいスキルなのだと思います。
☆オススメ理論書☆
▶ トニーのように“構造”から音楽を構築するために参考になる理論書:
・『マークレヴィン ザ・ジャズ・セオリー』(Amazonで見る)
※この本では、ジャズの構造や発想法が学べます。モードジャズなどでスケールの使い方に悩んでいる人に特におすすめです。
次回予告:第8回 ジャズ・クインテット再生の時代
1980年代、誰もやっていなかった“現代ジャズの王道”を選んだ理由
第8回では、トニーが再びジャズ・クインテットというフォーマットに戻った1980年代中盤を掘り下げます。
エレクトリックの時代にあえて“5人編成のアコースティックバンド”を選び、すべての曲を自作曲で固めた意味とは?
“伝統”と“革新”を同時に鳴らすバンド作りの哲学に迫ります。
【このシリーズの他の記事】
文・構成:浦島正裕(ジャズピアニスト/音楽理論講師)
ピアノと言葉を通して、日々、音楽の仕組みと心の動きの接点を探し続けています。
音楽の音にある「理由」を、常に多角的に考えています。
☆『THE PALM OF A BEAR』/浦島正裕
【クリエイティブノート】この連載は1992年にMusician Magazineに掲載されたTony Schermanによるインタビューを参考にし、独自の再構成と解釈を加えたフィクション形式の記事です。実在の発言内容を基にしていますが、構成上の演出や編集が含まれます。ジャズを学ぶ読者の学習と創造力を促す目的で制作しています。