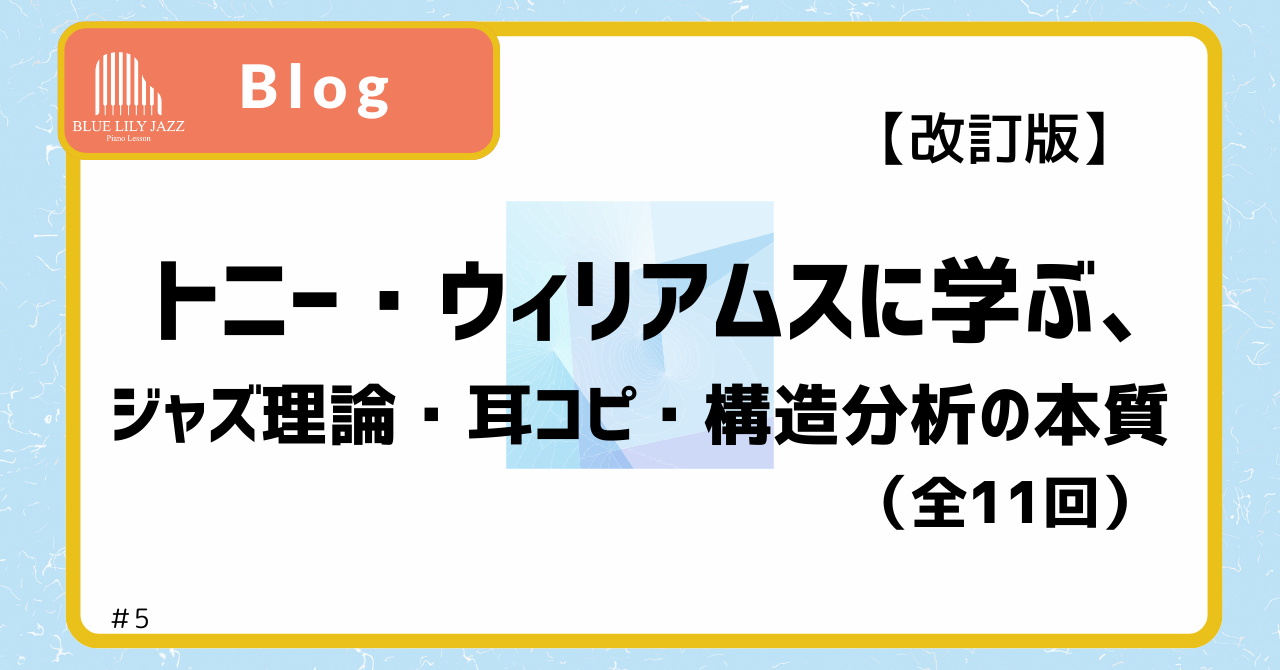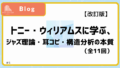第3回:トニー・ウィリアムスの作曲術|2本の指で始めた構造的ジャズ創作
トニー・ウィリアムス、『Life Time』と未完成から始まる創造
まずは聴いてみよう!⇒トニー・ウィリアムスの初リーダー作『Life Time』をAmazonで聴く
不完全な手で、完全な音楽を夢見る
インタビュアー:トニー、あなたの最初のリーダー作『Life Time』は、1964年に録音されましたよね。まだ18歳だったと思います。
トニー:そうだね。マイルスのバンドに入りたてで、まだ右も左もわからなかった頃。
だけど、どうしても「自分の音楽」を形にしてみたくなったんだ。
インタビュアー:当時、ピアノはどれくらい弾けたんですか?
トニー:正直に言うと、2本の指しか使えなかった(笑)。
右手でメロディ、左手でベースライン――コードなんてまだ弾けなかったよ。
でも、その中で「曲を作る」ってことがどういうことか、自分なりに掴みたかったんだ。
インタビュアー:2本の指だけで?
トニー:うん。でもね、面白いもので、制限があると逆に“音の選び方”に集中できる。
どの音を置くか、どう繋げるか、それを“耳”と“直感”で決めていくことが、作曲の本質じゃないかな。
☆トニーから学べること☆
きっとトニーは、「手が動かないから諦める」のではなく、「耳が動けば十分」と思っていたんだと思います。
楽器の技術が未熟でも、“音の構造を考える力”があれば曲は書ける。
その発想は、私たちにも勇気を与えてくれるものですね。
☆作曲に関する理論書☆
▶ トニーのように“構造”から音楽を構築するために:
・『ジャズにおける作曲の理論と実践 ジャズ・コンポジション』(Amazonで詳しく見る)
・ハーモニーに新しいカラーを加える リハーモナイゼーション・テクニック エクササイズと模範解答付(Amazonで詳しく見る)
※これら本では、作曲・リハーモナイズ・アレンジの発想法が学べます。リディアン的なトライアド配置や、モーダルな進行の中での“構造保持”に悩んでいる人に特におすすめです。
ハービー・ハンコックとの音の会話
ンタビュアー:『Life Time』のレコーディングには、ハービー・ハンコック(ハービー・ハンコックをAmazonで聴く)も参加していましたよね。
トニー:そう。ハービーは、僕のアイデアを“形”にする手助けをしてくれた。
たとえば、僕が2声でフレーズを提示すると、それにハーモニーを付けてくれたり、流れを補完してくれたり。
インタビュアー:彼は、あなたの書こうとしていることをどう理解していたんですか?
トニー:彼は感性と理論の両方を持ってたからね。僕の“感覚的なアイデア”を、理論的に正当化しながら整えてくれた。
「ここはパッシング・コードで色を変えてみよう」とか、「この音はLydianの響きを強調してるね」って具合に。
そういう会話を通して、僕自身も「この響きに名前があったのか」と学んでいけた。
☆トニーから学べること☆
理論は、表現の感覚を補完してくれる“翻訳装置”のようなもの。
ハービーとのやりとりを通じて、トニーは感覚と理論がつながる手応えを得たんでしょうね。
感じたものを他者と共有するには、理論の言語がとても大切になることを教えてくれます。
☆オススメ理論書☆
▶ トニーのように“構造”から音楽を構築するために参考になる理論書:
・『マークレヴィン ザ・ジャズ・セオリー』(Amazonで見る)
※この本では、ジャズの構造や発想法が学べます。モードジャズなどでスケールの使い方に悩んでいる人に特におすすめです。
荒削りだからこそ宿った“強さ”
インタビュアー:あなたはこの時点でまだ構成力も不十分だったと思いますが、『Life Time』の曲はどれも印象的です。
トニー:それはきっと、“未完成な感覚”があったからじゃないかな。
僕は設計図を引くというより、「この音に行きたい」という欲求に従って音を繋いでいった。
だから、理論的には変則的な構造でも、自分にはとてもリアルだった。
インタビュアー:自然に“語るような構成”ができていたということでしょうか?
トニー:うん。メロディに対して“対話”するセクションを置いたり、テーマを繰り返すけどハーモニーだけ変えたり――
今思えば、構成というより“ストーリー性”を大事にしていたのかもしれない。
演奏者にとって“語れる余白”を残しておくのが、あの頃の自分なりの作曲だった。
☆トニーから学べること☆
きっと彼は、完成度ではなく“衝動”を信じていたのでしょう。
だからこそ、あの荒削りな音楽がいま聴いても新鮮で、生き生きとしている。
未完成の中にある“何かを伝えたい”という欲望こそ、表現の最も強い動機なのかもしれません。
まずは聴いてみよう!⇒☆トニー・ウィリアムスの初リーダー作『Life Time』をAmazonで聴く
作曲とは「音をどう動かすか」の問題である
インタビュアー:当時、作曲の技術的な学びはどうされていましたか?
トニー:対位法から始めた。2声の動き、インヴァーテッド・カウンターポイント、フーガ、ソナタ形式……
それが自分の書いたメロディを“どう展開させられるか”のヒントになったんだ。
たとえば、Aメロのモチーフをミラー(反転)させてBメロに使うとか、
テーマのリズムだけを変形してブリッジにするとか。
そういう“モチーフの操作”って、演奏よりも構築的な楽しさがあった。
インタビュアー:つまり作曲とは、“音をどう動かすか”という視点?
トニー:そう。そしてその動きには必ず「意味」が必要なんだ。
理由のある転調、必然性のある終止――それができて初めて「曲」と言えると思う。
☆トニーから学べること☆
彼は、音楽を“動きの設計”と捉えていたんですね。
ただいいメロディを書くのではなく、それを“どう展開させるか”にこそ作曲の本質がある。
演奏で瞬時に反応する感性と、構造で支える知性の両方を持つことが、表現を豊かにしてくれるのだと思います。
☆オススメ理論書☆
▶ トニーのように“対位法”を勉強する人のために:
・対位法/矢代秋雄(訳)(Amazonで見る)
次回予告:第4回 Sister Cherylの秘密|トニー・ウィリアムスに学ぶ作曲とハーモニーの構造
トニーが目指した、“誰にでも届くメロディ”
第4回では、名曲「Sister Cheryl」に焦点を当てます。
ポップさと構築、複雑なハーモニーと歌えるメロディ、その両立を目指したトニーの挑戦。【名曲!「Sister Cheryl」をAmazonで聴く!】
そして、彼がハービーに語った「人が口ずさめる音楽とは?」という問いの核心に迫ります。
次回もお楽しみに!
【このシリーズの他の記事】
文・構成:浦島正裕(ジャズピアニスト/音楽理論講師)
ピアノと言葉を通して、日々、音楽の仕組みと心の動きの接点を探し続けています。
音楽の音にある「理由」を、常に多角的に考えています。
☆『THE PALM OF A BEAR』/浦島正裕
【クリエイティブノート】この連載は1992年にMusician Magazineに掲載されたTony Schermanによるインタビューを参考にし、独自の再構成と解釈を加えたフィクション形式の記事です。実在の発言内容を基にしていますが、構成上の演出や編集が含まれます。ジャズを学ぶ読者の学習と創造力を促す目的で制作しています。