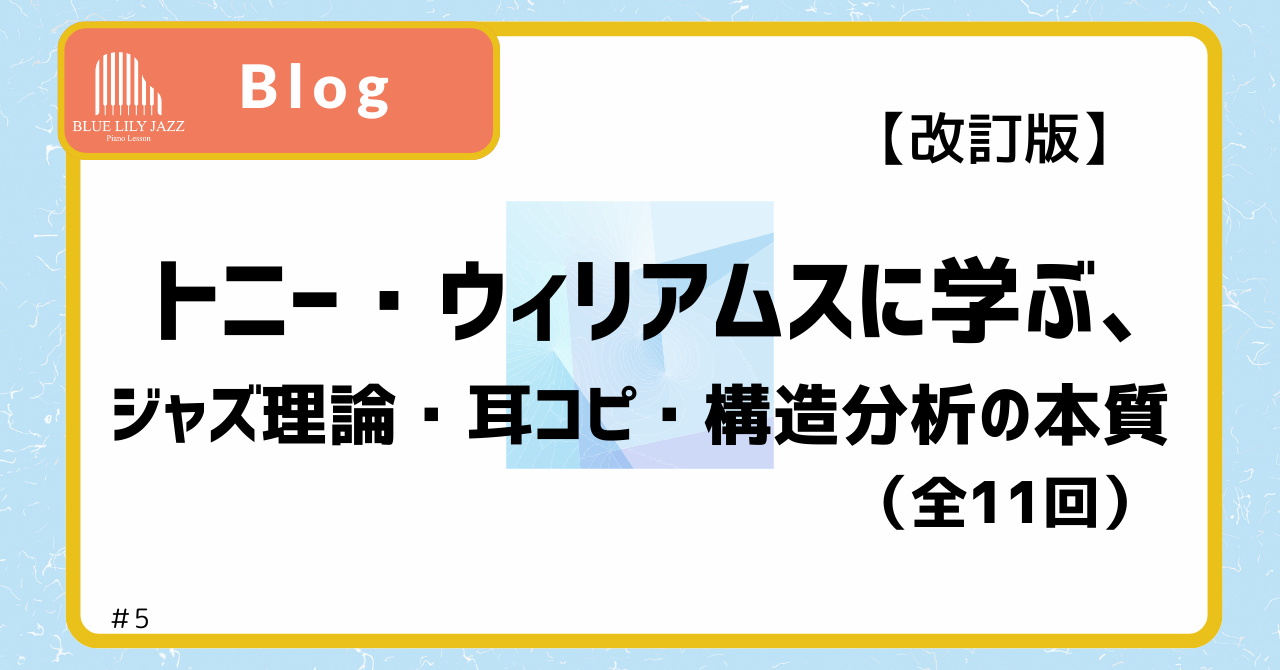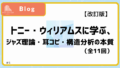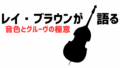第11回:トニー・ウィリアムスに学ぶ模倣と創造の本質|自由と構造のバランスを掘り下げる【後編】
トニー・ウィリアムス──彼が語った「音楽を建てる」という思想。
ドラムから始まった旅は、やがて作曲、構築、空間の設計へと広がり、最後には「問いを生きる音楽家」として完結しました。
この記事では、トニーの言葉をもとに、「音楽とは何か」を改めて探ります。
ドラムは語る道具。だけど語りきれなかった
インタビュアー:トニー、振り返ってみて、ドラムという楽器はあなたにとってどういう存在でしたか?
トニー:うーん……ドラムは最初の“声”だった。
でもね、ずっと“語りきれないもどかしさ”もあったんだ。
音階がない。ハーモニーがない。言葉にすればするほど制限があった。
だから、その制限をどう越えるか、というのが僕の人生だった気がする。
インタビュアー:その制限を超えるために、作曲や構築という表現に向かったんですね。
トニー:そう。自分が感じていることを、より広く、より長く、より深く伝えるために。
ドラムは“瞬間”を語る。作曲は“時間全体”を語る。
両方があって、初めて“自分を語る手段”が整ったんだよ。
☆トニーから学べること☆
トニーにとって“自分を語る”とは、手段を選ばず表現すること。
ドラムだけでは足りなかったけれど、ドラムがあったからこそ、自分の声を見つけられた。
どんな楽器であっても、その先に“自分の声”を探す旅が始まるのだと感じます。
音楽とは建築である――空間を設計するという視点
インタビュアー:あなたはかつて「音楽家は建築家であり、彫刻家でもある」と言いましたね。
その意味を、もう一度教えてもらえますか?
トニー:もちろん。僕にとって音楽は、時間の中に空間を作る作業だった。
ドラムの1拍1拍は、壁を立てたり、柱を置いたりするようなもの。
ハーモニーは光の角度で、リズムは床の材質みたいな感覚さ。
インタビュアー:それはまるで“音の家”を建てるような感覚ですね。
トニー:その通り。1曲書くときも、1ソロ叩くときも、「どんな空間が必要か?」を考えていた。
速くて細かいフレーズを積み上げたくなるときも、実は“静けさ”が足りないときだったりする。
そういう感覚があると、ただのテクニックとは全く違う“構築”ができるんだよ。
☆トニーから学べること☆
彼は音楽を“音の流れ”としてだけでなく、“空間のデザイン”として捉えていた。
その視点は、演奏にも作曲にも応用できる美しい考え方です。
音を積み重ね、流れを設計し、空間をコントロールする――それが“音楽を建てる”ということなのでしょう。
本当の声を探し続けた人生
インタビュアー:ドラム、作曲、室内楽、エレクトリックバンド――これだけ多様な活動をしてきて、最後に辿り着いたのは、どんな場所でしたか?
トニー:それは、“自分の声”かな。
模倣から始まって、自分で考えて、構築して、また壊して――
そのプロセス全部が、自分の「語り方」を探す旅だった。
他人のように叩くことも、他人のように書くこともできるけど、
結局それじゃ“トニー・ウィリアムス”にはなれない。
インタビュアー:それを見つけるのに、時間はかかりましたか?
トニー:めちゃくちゃかかった(笑)。
でもね、それが音楽なんだと思う。音楽は、何者かになろうとする旅なんだよ。
☆トニーから学べること☆
おそらく、どんな音楽家も「自分の声」を見つけるために旅をしている。
トニーはその旅を恐れず、常に問い直し、学び、構築し、崩し、また立ち上げた。
その姿勢が、彼の音にリアルな説得力を与えていたのでしょう。
終わらない問いに向かう力
インタビュアー:最後に、読者に向けて伝えたいことがあれば教えてください。
トニー:そうだな……音楽をやる人には、“答えを出そうとしすぎない”ことを伝えたい。
音楽は、問いかけることが仕事なんだ。
「なんでこのフレーズなんだろう?」「どうしてこの間なんだろう?」――
その問いを持ち続けられることが、ミュージシャンであるってことさ。
インタビュアー:問い続けること自体が、表現なんですね。
トニー:うん。“わからないまま進む勇気”を持つこと。
理論も技術も大事だけど、それを使って何を問いかけるか――
それがなければ、音はただの装飾になってしまう。
🎵 トニーの「問い続ける姿勢」に共鳴する一冊
トニー・ウィリアムスは、演奏でも作曲でも常に「問い続けること」の大切さを語っていました。
この「わからないまま進む勇気」を、もっと深く言葉にしてくれている一冊があります。
それが、ケニー・ワーナー著『Effortless Mastery(自由への音楽)』です。
音楽に限らず、表現を志すすべての人に、
「本当の自由とは何か?」を静かに問いかけてくれる名著です。
興味のある方はぜひ手に取ってみてください。
▶ Amazonで『Effortless Mastery(自由への音楽)』を見る
☆トニーから学べること☆
音楽とは「答えを持つこと」ではなく、「問いを生きること」なのかもしれません。
トニーの人生そのものが、“音とは何か”“自分とは何か”を問い続ける旅だった。
そしてその問いは、いま私たちの耳の中にも、問いかけ続けているように思います。
【シリーズ完結に寄せて】
トニー・ウィリアムスは、「ドラマー」の枠をはるかに超えて生きた音楽家でした。
彼のすべての言葉と演奏、そして沈黙の中にさえ、“構築された意思”が息づいています。トニー・ウィリアムスは、音を単なる流れではなく、「建築するもの」として捉えていました。
模倣から始め、理論を学び、構造を理解し、即興で語り、作曲で全体を語る――
そのすべての過程が、「自分とは誰か」という問いに向かっていた。
私たちが彼から学べることは、音楽的な技術やアイデアだけではありません。
「音楽を通して自分と出会う」という覚悟と誠実さこそが、彼の本当のレガシーなのです。
ドラムという声から始まり、音楽を設計し、空間を創り、自分自身を問い続けた旅路。
その姿勢は、「音楽を建てる」という発想そのものであり、今なお私たちに新しい問いを投げかけています。
📚 おすすめ書籍紹介コーナー
🎵 トニー・ウィリアムスの音楽観に共鳴するなら、次の3冊がおすすめです!
① ジャズ・スタンダード・セオリー(オサム・コウイチ)
ジャズスタンダード曲を、ハーモニーと構造から徹底分析する一冊。
「なぜこの進行になるのか?」を理論的に理解できる、実践派に最適なガイドブック。
② ザ・ジャズ・ピアノ・ブック(マーク・レヴィン)
世界中のジャズピアニスト必読の理論書。
コードワーク、モーダルアプローチ、即興の設計思想まで、ジャズの基礎を網羅できます。
③ザ・ジャズ・セオリー(マーク・レヴィン)
この本は、単なるコード理論の教本ではありません。
ハーモニー、モーダルアプローチ、リハーモナイズといった要素を、
「なぜそうなるのか」という視点で、論理的かつ実践的に紐解いていきます。
- ジャズの即興をもっと自由にしたい
- 曲の構造を理解して演奏に活かしたい
- ただ耳で覚えるだけでなく、理論で音楽を組み立てたい
そんな方に、心からおすすめできる内容です。
📖 音を真似るだけでは足りない。
「構造を理解して自由に語る」ために、確かな理論の土台を築きましょう!
【このシリーズの他の記事】
文・構成:浦島正裕(ジャズピアニスト/音楽理論講師)
ピアノと言葉を通して、日々、音楽の仕組みと心の動きの接点を探し続けています。
音楽の音にある「理由」を、常に多角的に考えています。
☆『THE PALM OF A BEAR』/浦島正裕
【クリエイティブノート】この連載は1992年にMusician Magazineに掲載されたTony Schermanによるインタビューを参考にし、独自の再構成と解釈を加えたフィクション形式の記事です。実在の発言内容を基にしていますが、構成上の演出や編集が含まれます。ジャズを学ぶ読者の学習と創造力を促す目的で制作しています。