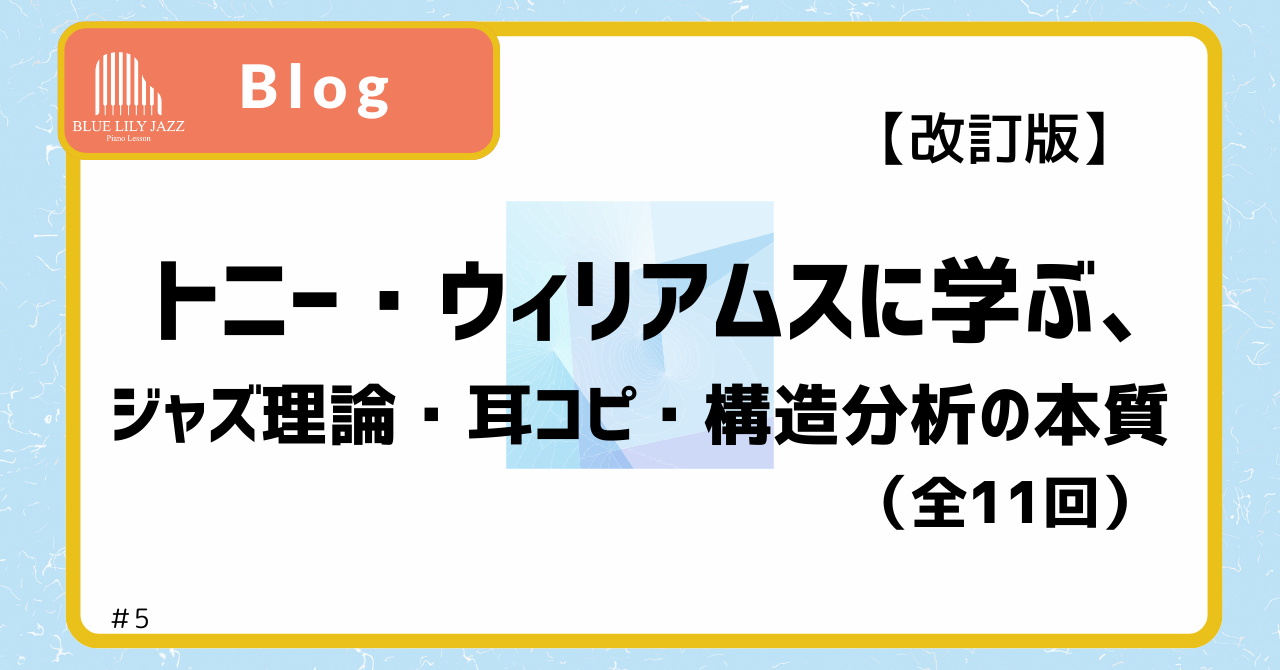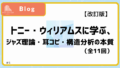第10回:トニー・ウィリアムスに学ぶ模倣と創造の本質|自由と構造のバランスを掘り下げる【前編】
トニー・ウィリアムス──彼が辿った「模倣と創造」の道。
13歳でドラムを始め、17歳でマイルス・デイヴィス・クインテットに参加した天才少年は、なぜ単なる演奏者に留まらず、作曲・構築へと進んだのか。
この記事では、トニーの言葉をたどりながら、「自由」と「構造」という2つのテーマを掘り下げます。
自由の器を広げるために、作曲を選んだトニー・ウィリアムス
インタビュアー:トニー、13歳でドラムを始めてから、17歳でマイルス・デイヴィスのバンドに加入。
まさに伝説的なスタートですね。でも、ご自身ではどんな思いでしたか?
トニー:それはね……いつも「これでいいのか?」という気持ちがあったよ。
もちろん演奏は好きだったけど、ドラムだけでは足りないって、どこかで思ってた。
感じているものを全部出せない。言葉で言えば“表現の器”が小さく感じられたんだ。
インタビュアー:だからこそ、作曲や構築に向かった?
トニー:そう。即興演奏では語れないことも、作曲なら語れる。
逆に、譜面では表しきれない“時間”や“呼吸”は、演奏でしか伝えられない。
両方やらなきゃ、自分の全部を伝えきれないって思ったんだ。
☆トニーから学べること☆
おそらくトニーにとって、音楽とは「自分を語るための手段」だったのでしょう。
ただ“技術を披露する場”ではなく、“自分とは何者か”を問い続ける過程そのもの。
だからこそ、演奏と作曲の両方を追い続けたのかもしれません。
「観察」と「構造分析」
インタビュアー:あなたは若い頃、マックス・ローチやアート・ブレイキー、フィリー・ジョーなどをそっくりにコピーしていたそうですね。
トニー:うん、それも2年、3年みっちりやったよ。
でもね、ただコピーしたんじゃないんだ。
「なぜこの音をここで入れたんだろう」「この沈黙の意味は?」――そうやって、行為の背後にある“意図”を見てた。
インタビュアー:模倣は分析の道具だった?
トニー:そう。真似ることが目的じゃない。
真似ることで、その人の考え方や構造を学ぶ。
模倣は入り口であり、そこから観察力と分析力が鍛えられるんだよ。
インタビュアー:理論的に掘り下げる感覚だった?
トニー:そうだね。聴いて、コピーして、なんでこうなってるのかを後から理論で説明する。
最初は耳、そのあとに知識が追いついてくる――その順番だった。
☆トニーから学べること☆
模倣という行為は、単なる“演奏の再現”ではなく、“構造の理解”でもある。
どこにどんな意図があり、どうしてその表現になったかを考える――
それこそが「真のコピー」であり、音楽理論の学習にも直結しているのだと思います。
もっと「模倣から自由へ」のプロセスを掘り下げたい方へ
演奏技術だけではたどり着けない、 「音楽と自分の心のあり方」を掘り下げる一冊。 耳コピや理論の先にある、“自由な表現”の本質を見つめたい方へ。
Effortless Mastery(自由への音楽)/ケニー・ワーナー著
演奏技術だけでは届かない、音楽と自己表現の核心を描いた名著です。
👉 Amazonで見る(Effortless Mastery)
演奏に潜む自由と責任──トニーの即興設計思想
インタビュアー:あなたの演奏には「自由さ」がある一方で、構造がとてもはっきりしています。
これは意識していたことですか?
トニー:当然だよ。自由には責任が伴うから。
ただ叩き散らすのは自由じゃない。
何を伝えたいか、そのためにどの構造を選ぶか――そういう“設計”をして初めて、演奏が自由になる。
インタビュアー:即興にも「構成」があるということですね。
トニー:そう。良いソロは必ず構造を持っている。
最初のモチーフを変形して展開したり、間合いを変えたり、流れが自然に感じられるように組まれてる。
それが“即興で作曲してる”ということなんだ。
☆トニーから学べること☆
自由とは、何でもできることではなく、「何をどう語るかを自分で決める力」なのかもしれません。
そのためには、理論や構造、展開の感覚が必要になる。
トニーの演奏は、まさに“考え抜かれた即興”の典型です。
◎トニーが所属したマイルス・デイヴィスの世界をもっと知りたい方へ
トニー・ウィリアムスが多大な影響を受けた、マイルス・デイヴィスの世界。 彼の「なぜこう演奏するか」「なぜこう作るか」という、 音楽哲学そのものに触れられる名著です。
『マイルス・デイヴィス自叙伝』
自由、即興、革新――マイルスの言葉から、トニーが何を感じ取ったかを想像してみてください。
◎耳コピと構造理解を実践するならこの1冊
トニー・ウィリアムスが歩んだ「模倣から構造理解へ」の道を、
実際にあなた自身の演奏・学びに活かしたいなら必携。
『ジャズ・スタンダード・セオリー』 ~名曲から学ぶジャズ理論の全て (CD付)
スタンダード曲を通して耳を鍛え、ハーモニーと展開を体系的に学べる一冊です。
👉 Amazonで見る(ジャズ・スタンダード・セオリー ~名曲から学ぶジャズ理論の全て (CD付))
模倣と創造のリアルな音源体験
◎トニー・ウィリアムスの若き日の「模倣と創造」を体感する
17歳のトニー・ウィリアムスがマイルス・デイヴィスのバンドで炸裂した、
歴史的ライブ音源「Four & More」。
ただのテクニックではない、“耳コピを超えた自由な表現”をリアルに感じることができます。
『Miles Davis – Four & More』(ライブ盤)
次回予告:トニー・ウィリアムスに学ぶ模倣と創造の本質|自由と構造のバランスを掘り下げる【後編】
・音楽を“建築”と捉える発想
・ドラム以外の言語で語ろうとした理由
・「トニー・ウィリアムスとは何者だったのか?」という問いへの彼自身の答え
をじっくり掘り下げながら、シリーズ全体を締めくくります。
【このシリーズの他の記事】
文・構成:浦島正裕(ジャズピアニスト/音楽理論講師)
ピアノと言葉を通して、日々、音楽の仕組みと心の動きの接点を探し続けています。
音楽の音にある「理由」を、常に多角的に考えています。
☆『THE PALM OF A BEAR』/浦島正裕
【クリエイティブノート】この連載は1992年にMusician Magazineに掲載されたTony Schermanによるインタビューを参考にし、独自の再構成と解釈を加えたフィクション形式の記事です。実在の発言内容を基にしていますが、構成上の演出や編集が含まれます。ジャズを学ぶ読者の学習と創造力を促す目的で制作しています。